
M&Aでは、シビアな法的判断が必要となり、弁護士の専門的な知識や交渉力がものを言う局面が多々あります。弁護士がM&Aで果たす役割や業務の内容、弁護士に依頼するメリットや費用相場などを詳しく解説します。(執筆者:京都大学文学部卒の企業法務・金融専門ライター 相良義勝)

M&Aにおいて弁護士は法的な側面について助言を提供したり、当事者の代理人として交渉を行ったりします。
検討段階から経営統合段階にいたるまで、M&Aの全プロセスに弁護士の関わる局面があります。
そのため、弁護士事務所のなかにはM&A全般についてのサポートを提供しているところもあります。
ここではまずM&Aにおける弁護士の役割を大まかに紹介し、公認会計士・税理士の役割との違いを確認しておきます。
個々の業務の内容については後ほどくわしく取り上げます。
M&Aは成就までに長い時間を要し、巨額の金銭・資産の移動、組織改編などを伴う一大プロジェクトです。
M&Aに関係する法的リスクを入念にチェックして対処方法を検討し、契約書や経営統合プランに的確に反映させておかないと、後になって取り返しのつかない事態に陥ることがあります。
弁護士は法律の専門家の立場から法的リスクをチェックし対策のための助言を提供します。
とくに、売り手企業の抱えるリスクについて内部情報をもとに精査する法務デューディリジェンスのプロセスと、契約書のレビュー(法的なチェック)については、弁護士への依頼が必須と言えます。
法的リスクを考慮した上で弁護士がM&Aスキームの提案や買収防衛策導入に関する助言を行うケースもあります。
契約書のレビューだけでなく作成そのものも弁護士に依頼するケースもよくあります。
スキームによっては、クロージング(譲渡や組織再編の実行)までに法律にしたがってさまざまな手続きや書面の作成を行う必要があり、弁護士はそれらが法にのっとって適切なタイミングで遂行されるようにサポートします。
M&Aの条件交渉や債権者などのステークホルダーとの交渉を外部の専門家に代行してもらう場合には、弁護士に依頼する必要があります。
そうした交渉は「法律事務」にあたり、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務に関する代理や仲裁を行うことは弁護士法で禁止されているためです。
弁護士事務所のなかには、戦略立案や買い手・売り手とのマッチング、企業価値算定、スキーム選択、プロジェクトの進行管理など、M&A全般についての専門的な助言(アドバイザリー)を提供しているところもあります。
公認会計士は財務面のサポートを提供します。
企業価値算定や財務デューディリジェンス(財務データの分析や会計処理の適正さのチェックなど)は公認会計士の役目です。
税理士は税金の専門家として税務デューディリジェンス(税務会計の適正さや税務調査・追徴課税のリスクのチェックなど)を行ったり、税制上有利なスキームを提案したりします。
弁護士事務所と同様に、会計事務所・税理士事務所のなかにはM&A全般に関するアドバイザリを提供しているところもあり、三者の違いがわかりにくいケースもあります。
基本的には、それぞれの事務所が専門業務(法務、財務、税務)を軸にして、必要に応じて外部の専門家と連携(例えば弁護士事務所が公認会計士・税理士などと連携)しながらM&A全般についてのアドバイザリを提供する形になっています。
アドバイザリ契約をする場合にはそれぞれの事務所の強みや料金体系を細かくチェックすることが重要です。

M&Aでは予期しないリスクが支障となって取引が不成立に終わるケースがよくあります。
また、後になってリスクが顕在化して大きな損害をこうむったり、相手企業から損害賠償を請求されたりするケースもあります。
デューディリジェンスを十分に行わないまま安易にM&A契約を結んでしまうと、不当な条件でM&Aを実施し会社と株主に損害を与えたとして、取締役が株主から善管注意義務違反で訴えられることもあります。
弁護士に専門的なチェックと法務デューディリジェンスを依頼することで、そうした危険を最小限に抑えることができます。
弁護士にM&A交渉の代理人となってもらうことで、相手企業に対する交渉力を補強することができます。
とくに、売り手企業が格上の買い手企業を相手にして交渉を行わなければならない場合には有効な選択肢です。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)や仲介会社などの専門業者にM&Aプロジェクト全体のサポートを依頼しているケースでは、業者に対する交渉力も重要になります。
FA・仲介会社にとってはM&A契約の成立によって得られる成功報酬が最大の収入源であるため、M&Aに関する依頼者のニーズを充足させることよりも成約の方を優先しようとするインセンティブが働きがちです。
また、FAは売り手・買い手の一方とのみ契約しますが、仲介の場合は売り手・買い手双方と契約を結び双方から成功報酬を得る仕組みであるため、利益相反が起こりやすい(とくに、より資金力があり今後も顧客となる可能性の高い買い手企業の側に寄り添った対応に陥りやすい)と指摘されます。
弁護士とも契約を結び、業者が提示する方針に関してセカンドオピニオンを提供してもらったり、業者との協議に介入してもらったりすることにより、自社の利益を守りながらより積極的に交渉していくことが可能になります。
M&Aでは、相手企業や株主、債権者、従業員などとの間で紛争が持ち上がるケースも少なくありません。
そうした場合、デューディリジェンスやM&A契約を担当した弁護士に間に入ってもらうことで、早期に紛争を解決し、訴訟やレピュテーションの悪化などの大きな問題に発展する前に収束させることが容易になると考えられます。
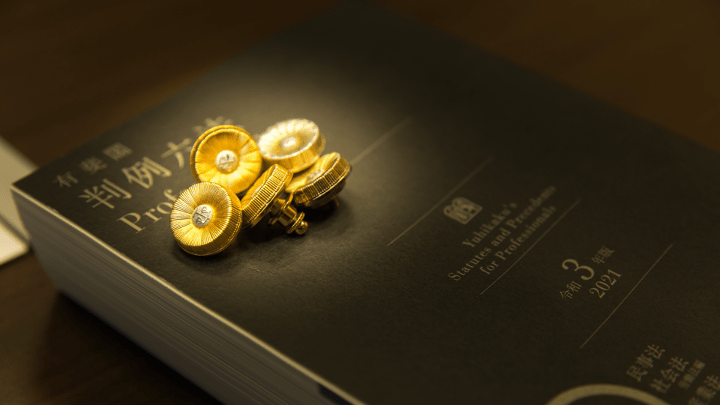
弁護士事務所のなかにはM&A全般に関するアドバイザリーを提供するところもありますが、ここでは弁護士特有の業務と言えるもののみを取り上げて解説します。
デューディリジェンスとは、売り手企業から提供される内部資料の調査や役員・キーパーソンとの面談、現場の視察などを通してM&Aに関わるリスク・問題点を抽出し、対応策を検討するプロセスのことです。
法的リスクに焦点をあてて行われるものを法務デューディリジェンスと呼びます。
法務デューディリジェンスの検討対象は以下のように多方面にわたり、それぞれが専門的な判断を要するため、弁護士への依頼は必須と言えます。
調査対象 | チェックすべき主なポイント |
株式 | 株式発行の有効性・適法性、現在の正式な所有者と譲渡履歴、譲渡制限の有無、株券発行会社の株券発行状況 |
契約 | 取引契約書の有効性、チェンジ・オブ・コントロール条項(契約の相手方に支配権の変動が生じた場合に契約の解除・変更を要求できるとする条項)などM&Aの支障となる契約条項の有無、口頭での約束や業界慣行の概要 |
知的財産権 | 保有する知的財産権の内容と帰属(会社保有か、オーナーなど個人の保有か)、他者とのライセンス契約の内容、他者の知的財産権に対する侵害行為の有無、職務発明(従業員が職務として行った発明)に関する規程や対価の適正さ |
労務 | 労働組合の有無、労働法関係のコンプライアンス、残業代未払いや労使間紛争の有無 |
許認可 | 事業に必要な許認可の取得・更新状況、M&Aにより必要となる申請・届出の有無 |
紛争・訴訟 | 係属中の訴訟・紛争の有無、過去の訴訟・紛争の内容、将来的に訴訟に発展する可能性のあるトラブルの有無と訴訟になった場合の影響の大きさ |
M&Aでは交渉を開始する段階でNDA(秘密保持契約)を結び、初期交渉がまとまった段階で基本合意書、最終条件の合意が得られた段階で最終契約書を締結するのが一般的です。
自社にとって不利な内容や将来の紛争の種になるような条項が契約書に含まれないように十分注意する必要があります。
スキームによっては最終契約書に記載しなければならない事項が会社法で定められており、それらを漏れなく適正に盛り込まなければなりません。
契約書(自社で作成したもの、または相手方から提示されたもの)を正確にチェックするためには専門的な知識と経験が求められるため、弁護士への依頼が欠かせません。
弁護士に契約書の起草・作成を依頼するケースもあります。
NDAには定番の条文構成がありますが、細部については実情に即して決めなければなりません。
M&Aでは大量の秘密情報がやり取りされ、M&A交渉を行っていること自体も重大な機密に属します。
弁護士にはプロジェクト全体の流れを踏まえて各条項をチェックしてもらうことが必要です。
基本合意書は、M&Aの基本条件(スキームや譲渡価格、役員・従業員の引継ぎなど)について定めた条項と、以降のプロセスの進め方について定めた条項からなります。
前者はあくまで暫定的な共通認識を定めたものに過ぎず、法的拘束力を持たせない(撤回しても法的責任を問われないようにする)のが普通です。
一方、後者にはデューディリジェンスの実施と売り手の協力義務、買い手への独占交渉権付与などを定め、法的拘束力を持たせるのが一般的です。
これらの条項については法的リスクを慎重に検討し、売り手・買い手の利害を調整する必要があるため、弁護士の関与がとくに重要となるポイントです。
上場企業の場合、基本合意の締結は適時開示の対象となる可能性が高いため、この点についても弁護士の関与が求められます。
デューディリジェンスは買い手側が売り手企業に対して実施するものですが、売り手側の協力がなければ成り立ちません。
そこで、基本合意書に売り手側の協力義務を規定しておきます。
買い手側としては協力義務の範囲を広くとり、具体的な拘束力をもつ規定にしたいところですが、売り手側としては協力義務を限定的なものとしておくのが有利です。
法的な利害の対立があるため交渉により調整する必要があります。
デューディリジェンスには大きなコストがかかるため、買い手側としては独占交渉権を要求する(売り手側に他の候補との交渉を禁じる)のが通例です。
一方、売り手側としては複数の候補と交渉してよりよい条件を提示する相手を探した方が有利です。
買主候補を安易に限定してしまうと、株主から善管注意義務違反で訴えられる恐れもあります。
そこで、利害調整のために独占交渉権には有効期間が設定されるのが一般的です。
さらに、他の候補からより魅力的な買収提案を受けた場合には(善管注意義務違反に問われないよう)条件の見直し協議を行うとする規定(フィデュシャリーアウト条項)を置く場合もあります。
上場企業の場合、株式投資者の判断に影響を与えるような重要事実が取締役会で決定された時点で適時開示を行う必要があるため、基本合意締結についての取締役会決議を行って時点でその内容を公表するのが一般的です。
何らかの理由でそれを避けたい場合には、特別な配慮が必要です。
基本合意が単なる準備行為に過ぎず、M&Aに関する重要事実がまだ決定にいたっていないと考えられる場合や、M&A成立の見込みが立っていない場合などには、適時開示は不要とされています。
そこで、M&Aの具体的な条件についてはあえて合意を避け、M&A交渉についてのごく一般的な規定のみを盛り込んだ基本合意書を締結する、といった対応をとるケースがあります。
こうした対応は証券取引所の上場規程やガイドラインに精通した弁護士と相談して決定する必要があります。
最終契約書にはスキームごとに一般的な条文構成のパターンがありますが、具体的な内容は個々のケースで千差万別です。
各条項の内容とリスクを弁護士に隅々までチェックしてもらう必要があります。
例えば、表明保証、取引保護、合意管轄などはとくに法的な利害の調整が必要になる条項です。
表明保証条項とは、M&A契約に関わる重要な事実関係・法律関係について相手方に表明し、保証する条項です。
とくに、重大なリスクが存在しないことを売り手側が表明・保証する条項が大きな比重を占めます。
デューディリジェンスでは時間や情報源の制約があるため、売り手企業の抱えるリスクをすべて洗い出すことは不可能です。
そこで、予期せぬリスクによる損害を回避するため、M&Aの支障になると考えられるポイントを列挙して、それに関して重大なリスクが存在しないことを売り手側に表明・保証してもらいます。
ただしデューディリジェンスで判明したリスクは除外します。
例えば、「税務申告を適正に行っており、当局から課税処分を受ける原因となる事由は存在しない」「第三者から訴訟を提起されるおそれは存在しない」といったものが、売り手側の表明保証条項の典型的な例です。
表明保証に違反する事実が明らかになった場合には補償を請求できるとする旨の条項を合わせて規定しておきます。
また、クロージング時点で表明保証への違反がないことが、クロージングの前提条件とされるのが通例です。
売り手側としては「存在しない」ことを無条件に保証するのはリスクが高い(後に補償を請求される恐れが大きい)ため、「合理的に知りうる限り(存在しない)」といった文言で限定することがあります。
また、完全な無違反をクロージング条件とするのは厳しすぎるため、「重要な点については(違反がない)」などと限定することも行われます。
表明保証条項についてはこうした表現上の問題も含めて弁護士と十分に協議する必要があります。
取引保護条項とは、別の買い手候補がM&A取引に介入することを防ぐための条項です。
例えば以下のような条項があります。
こうした条項は第三者の介入を一方的に排除し、売り手やその株主の権利を制限するものであるため、そのままでは裁判で効力が否定されたり、売り手側の取締役が善管注意義務違反に問われたりする恐れが高くなります。
したがって、一定期間は第三者との交渉を許す形にしたり、善管注意義務違反に問われかねない場合には取引保護条項に従わなくてもよいとする規定(フィデュシャリーアウト条項)を設けたりする必要があります。
取引保護の必要性を考慮しつつ、こうした点について弁護士と十分に協議した上で取引保護条項を設定することが求められます。
合意管轄条項とは、紛争が持ち上がった場合にどこの裁判所で第1審を争うかについて当事者間で合意した内容を規定しておく条項です。
合意管轄条項を設けない場合は法令に従って裁判所が決定されます(被告側の所在地の裁判所など)。
いざ裁判となった場合、裁判所が遠い土地にあると担当者や弁護士の出張コストが高額になってしまうため、とくに地理的に遠く離れた企業同士でM&Aを行う場合には注意が必要な条項です。
さらに、海外の企業との間で行われるM&A(クロスボーダーM&A)となると、コスト面の問題に加えて法制度の違いも考慮しなければなりません。
クロスボーダーM&Aでは、合意管轄の問題に限らず条件交渉やデューディリジェンスなど取引全般にそうした点が関係してくるため、相手企業の所在国の弁護士や相手国の法制度に精通する専門家から支援を受けることが必要になります。
M&Aでは当事者間で契約書を取り交わした後もクロージングに向けてさまざまな手続きを遂行する必要があります。
弁護士以外の専門家(FAや仲介会社など)によるサポートも行われていますが、広範囲の法律が関係し、条文内容も複雑であるため、弁護士にも関与してもらうのが安全です。
合併、会社分割、事業譲渡、株式交換、株式移転のスキームでは、会社法にしたがい、株主と債権者の権利を保護するための手続き(事前開示書面の作成と開示、株主総会開催、反対株主株式買取請求・債権者異議申立てに関する対応など)を遂行する必要があります。
また、会社分割の場合、労働契約承継法にしたがい、分割される事業に関係する従業員との協議などが必要です。
これらの手続きについて内容や期間・期限などが法令で細かく規定されています。
弁護士は手続きの適正さのチェックや適切なスケジュールの設定などの支援を提供します。
合併、会社分割、株式交換、株式移転を含むスキームでM&Aを行う場合、金融商品取引法により財務局に有価証券届出書を提出することが必要になるケースがあります。
M&Aの各当事者が属する企業グループの国内売上高が一定のレベルを超えるケースでは、事前に公正取引委員会に届出を行って独占禁止法上の審査を受けなければならないことがあり、そうなるとクロージングに向けたスケジュールに影響が出ます。
M&Aに際しての許認可の扱いは業法によりさまざまで、業種によってはM&Aで許認可を承継できず、買い手企業による許認可取得が必要になることがあります。
また、売り手企業が事業に必要な許認可を取得していなかったり更新していなかったりするケースでは、クロージングまでに申請しておくなどの対応が求められます。
弁護士は許認可申請の要不要について検討し、当局との交渉、提出書類のチェック・作成、申請代行などを行います。
弁護士は依頼者の代理人として相手企業や債権者などと直接交渉を行うことができます。
条件交渉についてはFAや公認会計士・税理士などの他の専門家も助言や提案を行うことはありますが、弁護士はそうしたことも踏まえつつ、相手方と直接交渉する役目を担います。
また、M&Aでは比較的初期の段階に経営トップ同士の面談が行われるのが通例ですが、弁護士が間に入ってアレンジなどを行うことでスムーズな面談が可能となります。
M&Aの影響を受けるステークホルダーとの交渉も弁護士が担当することができます。
金融機関などの債権者との交渉はとくに弁護士が活躍する場面です。
例えば、中小企業が売り手となるM&Aでは引退するオーナー経営者の個人保証の扱いがしばしば問題となり、売主としては個人保証の解消を譲れない条件として要求します。
最終的には買い手側の責任で保証の解除のための協議や手続きを行うことになるのが一般的で、弁護士は金融機関との交渉などを担当します。
M&Aにより事業再生を図るケースでも、弁護士と金融機関の交渉が鍵となります。
M&Aは債務超過企業の再生のために利用されることがあります。
資金力のある企業に会社を売却してその傘下に入って再生を図る方法と、優良事業のみを会社分割・事業譲渡によって切り出してスポンサーとなる企業(ファンドなど)に売却し、残った事業については債務整理を行って解散するという方法があります。
そうしたケースでは、M&Aのスキームや事業再生の見通し、債務の弁済方法、債権放棄などの金融支援をめぐって、売り手企業、スポンサー(買い手企業)、債権者である金融機関との間で複雑な利害調整が必要になります。
弁護士はスポンサー・金融機関と利害調整のための交渉を行い、債務整理の手続きをサポートします。
事業生成スキームの構築など、全般的なアドバイザリーを提供する場合もあります。
売り手企業の重要な取引先との契約にチェンジ・オブ・コントロール条項が含まれている場合、経営統合に支障が生じる恐れがあるため、取引先から事前に取引継続の同意を得る必要があります。
また、中小企業などでは契約関係があいまいなまま取引が継続されている場合があり、M&Aをきっかけにして取引の打ち切りや見直しが求められたりするケースがあります。
弁護士はそうしたケースで取引継続に向けた交渉を担い、今後を見据えて契約関係の整備を行います。
基本合意や最終契約まで進んだ後になって、重大なリスクが明らかになったり見解の対立が生じたりした結果、取引の中止(ディールブレイク)が検討されることがあります。
その際、基本合意・最終契約の解釈をめぐって紛争が生じたり、相手方から契約違反として損害賠償を請求されたりするケースがあります。
また、M&A成立後に表明保証に反する事実が判明したとして補償の請求がなされることもあります。
こうした場合、弁護士は法的知識を駆使して紛争を処理し、穏便な形でのディールブレイクや請求取り下げの実現を図ります。
M&A契約や法務デューディリジェンスを担当した弁護士が関与すれば、よりスムーズな解決につながると考えられます。
弁護士事務所によっては、スキーム構築や買収防衛策導入など、M&Aに関する戦略的なプランニングも行う場合があります。
弁護士は売り手企業が抱える法的リスクを評価した上で、できる限りリスクを小さく抑えながらM&Aの効果を最大化することができるスキームを提案します。
これは買い手企業にとってだけでなく、有利な条件で譲渡を行いたい売り手企業にとっても重要です。
例えば、売り手企業の債務の一部を承継対象から外すために事業譲渡や会社分割のスキームを検討するケースがあります。
事業譲渡・会社分割では基本的には承継する権利義務を選別することができ、承継対象から外した債務については買い手企業に履行の義務が生じません。
ただし、買い手が売り手の商号を引き継ぐ場合や、売り手企業に残される債務の債権者が損をすることになる(例えば確実に貸し倒れになる)ことを知りながら事業譲渡・会社分割を行った場合などには、買い手側にも履行義務が生じる可能性が出てきます。
また、事業譲渡では権利義務を個別に承継する手続きが求められるため、そのためのコストも考慮しなければなりません。
こうした点を総合的に勘案して具体的なスキームに落とし込むためには専門的な判断が必要になります。
買収防衛策は買収者を排除する効果だけを考えるのではなく、株主の権利や市場に対する透明性も考慮した上で導入する必要があります。
買収に対する防衛策は、企業価値と株主の共同利益を保護することを目的として導入するのが原則です。
現経営陣・特定株主の支配権の維持や、買収者を一方的に排除することを目指して防衛策を設定してしまうと、裁判で否認される可能性が高くなります。
防衛策を平時から十分に開示しておくなど、公平性・透明性を確保するための手続きも求められます。
買収防衛策は関係する法律や判例、各種ガイドラインなどに精通した専門家の助言のもとで導入するのが安全です。
デューディリジェンスで把握された法的リスクのなかには、M&A成立後の経営統合作業(PMI)で解消していかなければならないものがあります。
また、人員整理や労働条件変更など、難しい法律問題をはらんだ施策を実施する必要に迫られることもあります。
こうした課題に関しては、企業法務に精通した弁護士にサポートを依頼するのが得策です。
法務デューディリジェンスを担当した弁護士にM&A成立後も継続してサポートを依頼すれば、よりスムーズな対応が可能になると考えられます。

M&Aで弁護士に支援を依頼する形態は以下の3つに分けることができ、それぞれに一般的な料金パターンが存在します(ただし具体的な金額は業者により異なります)。
作業にかかった時間数に応じて料金が請求される場合と、内容や規模に応じて1件ごとの固定料金が設定されている場合があります。
依頼内容 | 時間制 | 固定制 |
契約書のレビュー・作成 | 1時間あたり数万円~10万円程度 | 50万円~数百万円 |
法務デューディリジェンス | 1時間あたり数万円~10万円程度 | M&Aの規模や調査対象の範囲・深さにより異なる 例:小規模案件(買収価格数億円以下)で50万円~数百万円、中規模案件(買収価格10億円~数十億円)で数千万円、大規模案件(買収価格100億円以上)で1億円~ |
月額報酬が一般的です。
顧問業務の範囲・内容により、月額数万円~数十万円といった幅があります。
M&Aアドバイザリー契約では、着手金、リテイナーフィー(月額顧問料)、中間報酬(基本合意成立時などに請求)、成功報酬(最終契約成立時に請求)という料金構成が典型的とされますが、実際には事務所の方針により料金体系は異なります。
近年では成功報酬のみというケースが増えているようです。
成功報酬の計算にはレーマン方式が用いられるのが一般的です。
レーマン方式では下表のようにM&A取引金額を5つの部分に分け、それぞれの部分に一定の手数料率をかけて足し合わせることにより報酬を算出します。
例えば8億円の取引であれば「5億円×5%+(8億円-5億円)×4%=3,700万円」となります。
取引金額は「買収価格」とする場合と「買収価格+売り手企業の有利子負債(銀行からの借り入れなど利子を伴う負債)総額」とする場合があります。
取引金額の区分 | 手数料率 |
5億円以下の部分 | 5% |
5億円超10億円以下の部分 | 4% |
10億円超50億円以下の部分 | 3% |
50億円超100億円以下の部分 | 2% |
100億円超の部分 | 1% |
M&A法務は弁護士にとって一般的な業務とは言いがたく、弁護士事務所により対応力には大きな差があります。
M&Aに強い弁護士事務所を選ぶには、幅広い法的問題への対応力、M&Aに関する実績、交渉力、他の専門家との連携力・コミュニケーション力といった観点で弁護士事務所を比較するのがよいでしょう。
M&Aでは会社法を始め、金融商品取引法、独占禁止法、知的財産権法、労働法、各種の業法・規制など、非常に広範囲の法令が問題となり、状況に応じて法的知識を組み合わせて総合的な解決を図ることが求められます。
M&Aに関して有効な支援を提供するためには、幅広い法的問題について横断的に対応できる弁護士事務所である必要があります。
詳細なデューディリジェンスの遂行、経営統合に向けた法的リスクの評価と対応策の提案、スキームに即した契約書作成と手続きのサポートなど、M&Aには特有の法的課題が多々存在し、しかもそれらを解決するために大量の業務を限られた時間で的確に遂行していく必要があります。
そうした遂行能力はM&Aに関する豊富な経験の上に成り立つものです。
所属する個々の弁護士の経歴に加え、弁護士事務所のチームとしての実績も重要なポイントです。
M&A交渉の代理人となる弁護士には、さまざまな局面でさまざまな相手(売り手または買い手企業の担当者や経営陣、金融機関、取引先、監督官庁、従業員など)とコンタクトをとり、積極的に交渉を展開する能力が求められます。
M&Aは総合的なプロジェクトであり、デューディリジェンスやスキームの検討、条件交渉などにおいて、財務や税務、環境、ITなど、法律以外の分野の専門家との連携が必要になります。
FA・仲介会社の采配のもとでM&Aを進め、法務デューディリジェンスのみをスポットで弁護士事務所に依頼するような場合には、コミュニケーション力に秀でた弁護士に担当してもらうのが望ましいと言えます。
また、弁護士事務所にM&Aアドバイザリを依頼するケースでは、実績のある公認会計士や税理士との間にしっかりとした連携体制を構築している弁護士事務所を選ぶことが重要です。
M&Aでは初期段階から経営統合プロセスにいたるまで多種多様な局面でシビアな法的判断が必要になります。
とくに契約書作成と法務デューディリジェンスでは弁護士の関与は必須です。
その他、相手企業やステークホルダーとの交渉、スキーム選択、クロージングに向けた手続きなど、弁護士の専門的な手腕が生きる場面が多々あります。
弁護士に支援を依頼する側としては、予算や時間の制約を考慮しつつ、依頼する業務の範囲や深さを慎重に検討し、自社のニーズに合った強みを持つ弁護士事務所を選定することが重要です。
(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)