業務提携とは?メリットや進め方、資本提携・M&Aとの違い
- 執筆者: 相良 義勝 (京都大学文学部卒 / 専業ライター)
業務提携は他社の資源を活用して事業成長を図る施策のひとつです。同様の施策である資本提携・M&Aとの違いや、業務提携の種類、メリット・デメリット、進め方、契約方法、事例を解説します。
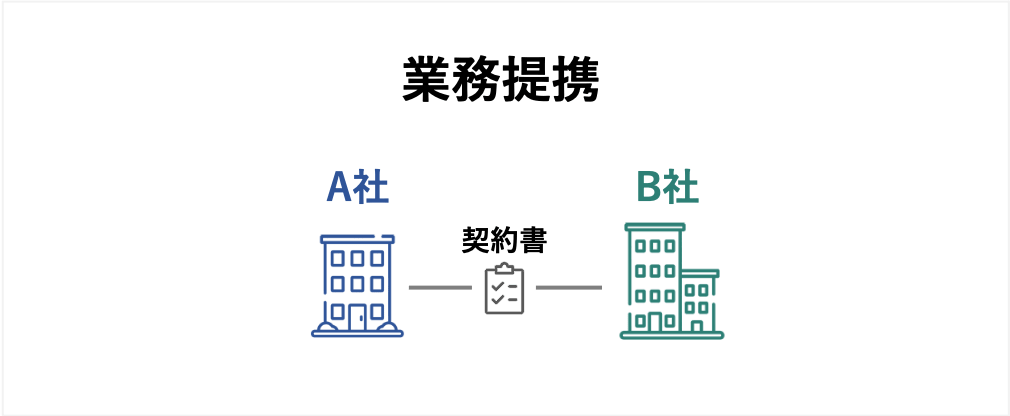
業務提携とは、複数の独立した企業が経営資源を出しあって協力体制を築き、一社単独では達成が難しい課題を解決して競争力向上や事業成長を図る施策です。提携する分野や目的、企業間の関係などにより多種多様な業務提携の形態が生じ、それぞれの形態に応じた契約が取り結ばれます。
業務提携と同様の目的で取り交わされる企業間契約に資本提携とM&Aがあり、業務提携は業務委託とも共通した側面を持っています。業務提携、資本提携、M&A、業務委託には根本的な相違点がありますが、戦略上の選択肢として相互に比較検討される対象でもあります。
業務提携の典型的な類型として、販売提携、技術提携、共同開発提携、生産提携の4つがあげられます。他に調達提携、流通提携、包括提携などがあります。
製品の開発力・供給力に優れたA社と販売力に優れたB社が提携し、B社の販売資源(販売網・人材・販促ノウハウなど)を介してA社製品の販売を行うのが販売提携です。販売提携には以下のような契約形式があります。
B社がA社製品を購入し、自らの計画と管理に基づいて販売を行う形式です。B社は自由に価格設定などを行える反面、自社で在庫を抱え、購入者に対して直接的に責任を負うことになります。
B社がA社の販売活動を代理し、A社の在庫をA社の販売計画・管理に基づいて販売する形式です。A社が価格設定などを自らコントロールし、購入者に対して直接的に責任を持つことになります。
本部企業(フランチャイザー)と複数の加盟店企業(フランチャイジー)の間で取り結ばれる契約で、以下の3つの要素を持っています。
A社が有する技術資源(知的財産権、ノウハウなど)をB社に有償で提供し、B社がそれを用いて開発・生産などを行うのが技術提携です。両者が互いに独自の技術を提供しあうパターンもあります。
複数の企業が技術力・開発力や人材・資金などを持ち寄り、共同で新しい技術や製品の開発を目指すのが共同開発提携です。当事者が互いに技術を提供しあうという意味で、技術提携の一種とも言えます。
A社がB社に生産方法や仕様を提供し、B社の生産力を自社の管理のもとで活用するのが生産提携です。B社から見れば、A社のノウハウやブランドを活用して生産事業の競争力を高めるのが生産提携であり、販売提携の側面も合わせ持っています。生産提携の代表例としてOEMとODMがあります。
A社(委託者)が提供する設計・生産方法の詳細や技術指導に基づき、B社(受託者)がA社ブランドの製品を生産する形態をOEMと呼びます。B社から見れば自社の製造品をA社のブランドで販売するということになります。
B社(受託者)が開発・設計から生産まで行った製品をA社(委託者)が自らのブランドで販売する形態をODMと呼びます。A社が製品の開発・設計と生産をB社に委託する場合と、B社が開発済みの製品をA社に売り込む場合があります。OEMよりもさらに販売提携の要素が強い形態だと言えます。
先進国大手企業が委託者となり、特定分野について高い技術力を持つ開発途上国企業が受託者となるのがODMの典型的なケースです。
商品・原材料・部品を共同で購入する調達提携や、物流施設の共同利用や販売先への共同配送を行う物流提携などがあります。
また、複数の事業分野にわたって提携して総合的な協力体制を築く包括提携という形態もあります。
業務提携と資本提携・M&Aは資本の移動の有無という点で異なり、資本提携とM&Aは支配権(経営権)の移動という点で異なります。
2社(の株主)の間で株式が譲渡・交換されたり、自己株式(会社が保有している自社株)や新株の取得を通して増資が行われたりすることを資本の移動と呼びます。業務提携は資本の移動を伴わない契約による協力関係の構築です。一方、資本提携とM&Aは資本の移動により行われます。
M&Aでは資本の移動(例えば全株式や過半数株式の取得)により買収側が相手企業の支配権(経営権)を獲得し、相手企業を吸収したり、子会社化したりします。資本提携では支配権の移動が起こらない範囲で株式取得が行われ、基本的には2社が独立したままで財務支援や業務提携の関係が結ばれます(資本提携を通して業務に関する提携を結ぶことを「資本業務提携」と呼ぶことがあります)。
資本提携は資本の移動を伴うという意味でM&Aの一種と言えます。業務提携はその点ではM&Aや資本提携と根本的に異なりますが、他社の経営資源を活用して事業成長を図るという目的は共通しており、M&A・資本提携と並べて比較検討されるべき選択肢となります。
例えば、M&Aによる買収を検討していた企業が、費用対効果や実行可能性を精査した結果、業務提携でも十分に目的が果たせるという結論に達することもあり得ます。
委託側が原料や製造方法を提供したり、取引基本契約を締結して継続的に委託したりするようなケースでは、業務委託は業務提携にかなり似てきます。また、販売提携・生産提携の契約書には販売委託や製造委託に関する条項が含まれることがあります。
とは言え、販売提携では互いに製品供給力と販売力を優先的・独占的に提供しあい、協力して販促活動を行うなど、一取引先というにとどまらない関係を構築します。生産提携では委託側の技術・ノウハウの提供と受託側の生産力の提供とが密に絡まりあい、OEM・ODMではブランドを介した太いつながりがあります。
業務委託の発注者・受注者として取引関係を結ぶにとどまらず、互いを事業成長に必要な相手と見なして密な関係を構築・維持するのが業務提携だと言えます。
業務提携には他社の経営資源の活用からもたらされるさまざまなメリットがあります。また、資本の移動を伴う資本提携・M&Aと比べてコストや手続きが少なくてすみ、互いの独立性も高く、機動的な運用が可能です。
他社経営資源の活用でもたらされるメリットについて、業務提携の類型ごとに簡単に整理しておきます。
製品を供給する側としては自社に欠けた販売力を補って製品の販路や認知度を拡大することができ、供給を受けて販売する側としては優先的・独占的な販売権を得て安定的な販売・営業活動を展開し、売上や実績を積み上げることができます。
技術提供側としては、主力事業に属する技術の業界内シェアを高めたり、活用度の低い知的財産権や物的資源から収入を得たりすることが可能です。提供を受けて技術を利用する側としては、研究開発費用の抑制、新製品開発サイクルの短縮などの利点があります。
各自のリソースを持ち寄ることで技術力の次元をアップし、一社だけでは不可能な新規開発を可能にする効果が期待できます。研究開発にかかる期間・コストも削減可能です。
生産を委託する側としては、自社で生産するよりも低いコストで製品在庫をそろえることができ、販売事業や他の製品(新製品)の開発に余力を注ぐことができるようになります。生産能力を欠いた企業であっても、委託先からの製品供給により自社ブランドを構築・拡充することが可能です。
生産を受託する側としては、生産規模を維持・拡大したり、生産余力を効率的に活用したり、大手企業や有名ブランドの製品を製造することを通してノウハウや実績を蓄積したりすることができます。
調達提携では、発注を大規模化することでスケールメリットによるコスト削減が達成できます。物流提携では、倉庫などの物流施設の有効利用、流通ネットワークや在庫管理の最適化、人材不足の解消などが期待できます。
業務提携にメリットをもたらす要素が、裏を返せばデメリットにもつながります。
業務提携では経営資源や内部情報を相互に公開するため、自社の技術・ノウハウが業務提携以外の目的で利用されてしまうリスクや、情報が外部に流出してしまうリスクがあります。自社が他社の技術を意図せずに盗用する形になってしまったり、他社の情報を誤って流出させてしまったりするケースも問題です。
そうしたことを防ぐために秘密保持契約の締結や情報管理体制の構築が行われますが、アウトとセーフを明確に線引きしたり、秘密情報や事業メンバーの行動を厳格に管理したりすることは容易とは言えません。
資本の移動がなく、比較的身軽な提携が可能だということは、裏を返せば提携関係が希薄化しやすいことを意味します。業務提携を担当するキーパーソンの異動をきっかけにして提携関係が希薄化し自然消滅に向かってしまうケースもまれではありません。
業務提携に向けた交渉や手続きの流れは以下のようになります。必ずしも以下のすべての項目を実施するというわけではなく、4の「基本合意締結」や5の「DD(デューディリジェンス)」は省略されることもよくあります。
各プロセスについて細かく見ていきましょう。
現状の分析に基づき、他社の経営資源の活用が必要と考えられる事業分野と課題を抽出し、業務提携の目的を明確化します。
そして、自社にとって武器となる経営資源と欠けている経営資源を見極め、目標達成と提携交渉のための戦略を具体化していきます。場合によっては資本提携やM&Aも選択肢に含めて複眼的に検討を加えます。
目的と戦略があやふやなままでは、業務提携の相手探しや交渉もままならず、実効性のある提携契約につながりません。
自社の目的と戦略に合致し、高いシナジー効果(協力による相乗効果)が期待できる提携先候補を探します。有望な相手が見つかり提携交渉を打診する際には、自社の強みや提携によって得られるシナジー効果などを整理して相手に的確に伝えることが重要です。
提携交渉開始の合意が得られたら、秘密保持契約を結んだ上で本格的な交渉に入ります。
業務提携では技術・ノウハウなどの内部情報や個人情報を互いにやり取りすることになります。そうした情報は交渉段階でもとり交わされ、業務提携交渉を行っているということ自体も秘密情報となります。したがって、交渉の初期段階から秘密保持契約を結ぶことが必要です。
秘密保持に関しては、最終的な提携契約や提携開始後の個別契約でも必要に応じて条項を設けて対応していきます。
交渉がある程度まとまった段階で、業務提携の基本的な内容や条件についての共通認識を整理した基本合意書を取り交わします。
第三者との提携交渉を禁止する(独占交渉権を付与する)条項や、次のプロセスで行われるDD(デューディリジェンス)への協力義務を規定する条項を盛り込む場合もあります。
基本合意によってこれらの点を明確化しておくことで、以後のプロセスを円滑にし、提携の実現可能性を高める効果が期待できるとともに、交渉が破綻した場合のコストを相手企業と分担することが可能になります。
ただし、業務提携では基本合意締結が省略されるケースもよくあります。一方、M&Aや(資本移動の金額が大きい)資本提携の場合には独占交渉権・DD協力義務を盛り込んだ基本合意が交わされるのが一般的です。
最終交渉に入る前に、提携事業の実行可能性について多角的に調査するフィージビリティ・スタディや、提携先企業の抱えるリスクを内部情報に基づき調査するDD(デューディリジェンス)が行われます。
業務提携では(資本提携やM&Aと違い)DDは限定的な側面について手短に行われるのが通例です(省略されることもあります)。
業務提携が事業として成り立つのかどうか、社内リソース、業務体制、資材・資金の調達、費用対効果、市場動向、法規制などの多角的な側面から調査します。情報分析だけでなく、相手企業の役員・キーパーソンとの面談や工場などの現地視察も行われます。
財務・法務などの各方面について、契約の成立や実行の支障となる問題がないかどうか調査することをDD(デューディリジェンス)と呼びます。
業務提携では包括的なDDは行わず、提携事業にかかわってくるような第三者との契約・取引関係のチェックなどに限定して調査が行われるのが通例です(DDをまったく行わないケースもあります)。
条件交渉や調査と並行して、プロジェクトチームを編成して社内体制づくりを進め、提携相手との相互協力体制(人事交流や定例ミーティングの開催、業務スケジュールの調整など)についても検討していきます。これらの取り組みは業務提携を実効性のあるものとするために欠かせません。
必要に応じて社外の専門家のアドバイスも得ながら、業務提携の内容・条件を検討し、相手企業と最終的な交渉を行って業務提携契約を締結します。相互協力体制に関する規定も契約書に盛り込んでおきます。
業務提携契約に基づいて業務を行っていきます。必要に応じてさらに個別に取引契約を結んで提携内容を具体化・肉付けしていく場合もあります。
ここでは業務提携契約の典型的な類型(販売提携・技術提携・共同開発提携・生産提携)を取り上げ、各類型に特有の条項と検討事項をくわしく見ていきます。
販売を引き受ける側にとっては、独占的販売権を得たほうが販売活動をしやすく、提携のメリットが大きくなるのが一般的です。
一方、販売を任せる側(製品供給側)としては、独占的販売権の付与はリスクが大きい選択肢です。その製品の売上について完全に提携先に依存することになるからです。
提携先の販売戦略が失敗したり販売促進のための努力が十分になされなかったりすればダイレクトに大きな損失をこうむります。
そのため、非独占的な販売権にとどめ、自社でも販売を行ったり第三者にも販売権を付与したりする余地を残しておくという選択肢も合わせて検討する必要があります。あるいは、販売を許可する地域を限定するということも考えられます。
独占的販売権を付与する代わりにノルマ(最低取引数量)を設定するという方法もあります。
独占的販売権を与える場合、製品供給側は失敗のリスクを抑えるためにある程度まとまった量の取引数量を提携先に求めるのが一般的です。例えば、1か月あたりのノルマ(最低取引数量)を設定し、ノルマ以上の数量を販売するか在庫として引き受けることを義務とします。
この義務は単なる努力目標として設定されるケースと、違反した場合にペナルティが課されるようにしておくケースがあります。ペナルティとしては、契約解除、契約内容変更(例えば独占権から非独占権への変更)、損害賠償請求などが規定されます。
販売を任せる側としてはペナルティを設定したほうが確実ですが、販売を引き受ける側としてはノルマを努力目標にとどめておくほうが有利です。
販売提携の形式には販売店形式・代理店形式・フランチャイズ形式などがあります。フランチャイズ形式の場合は独自の仕組みが存在していてそれに沿って契約交渉が行われるのが通例ですが、販売店形式と代理店形式の場合は個別の交渉によりいずれにするかが決定される場合もあります。
販売店形式の場合、販売を引き受ける側が販売価格のコントロール権を持ち、在庫を抱えるリスクを抱えることになります。代理店形式の場合は販売を任せる側がその立場に立ちますが、在庫のリスクについては最低取引数量を設定することである程度カバーできます。
また、販売店形式では販売を引き受ける側が(代理店形式では販売を任せる側が)購入者から直接的に責任を追及される立場に立ちますが、責任の分担に関する規定を盛り込むことで調整することも可能です。
このように販売店形式と代理店形式をめぐっては当事者間に利害の対立があるため、関連する条項で調整しながら契約を進める必要があります。
販売促進のための共同事業や協力義務に関する規定が契約に盛り込まれる場合があります。その場合、販売促進の方法や費用負担の割合、ノウハウ・人員の提供などが検討事項となります。
販売提携先が取り扱う商品のなかに競合他社製品が含まれていると、販売を任せる側にとっては販売提携の効果が相殺されてしまう恐れがあります。そのため、契約書に競合製品を取り扱わないという義務(競業避止義務)が盛り込まれる場合があります。
ただし、販売提携先の自由を過度に制限してしまう内容の契約は不当な拘束条件のついた取引(独占禁止法第2条第9項第6号ニ[1]、不公正な取引方法第12項[2])と見なされ、独占禁止法違反となる可能性があります。
技術提携契約はライセンス契約の一種です(技術の使用権を提供する側はライセンサー、提供される側はライセンシーと呼ばれます)。
特許などの公に登録された技術をライセンスする場合には登録内容により技術の範囲を特定できますが、ノウハウをライセンする場合にはノウハウの内容を契約書にできる限り具体的に記述して特定しておくことが必要です。
また、ライセンシーが技術を競合品に使用してしまう恐れもあるため、ライセンサーとしては提供する技術の用途を制限することを検討する場合があります。
ただし、競合品の製造そのものをライセンシーに禁じるような契約は、不当な拘束条件のついた取引(独占禁止法第2条第9項第6号ニ[1]、不公正な取引方法第12項[2])に該当する可能性があります。
ライセンス契約では使用権を独占的なものとするかどうかが重要なポイントです。ライセンシーとしては独占的使用権を得た方が有利ですが、ライセンサーとしては非独占的使用権にとどめておいたほうが選択肢が広がり、リスクを低減できます。
独占的使用権を認めるのと引き換えに、ライセンシーにミニマムロイヤリティ(後述)の支払いを求めることで利害を調整する場合があります。
技術の使用料には以下のような種類があります。
一般的には頭金のことです。技術情報の開示に大きなリスクが伴うと考えられる場合には、情報開示料として設定されることもあります。
例えば、ノウハウは特許などと比べて法律上の扱いが不明確で、情報漏洩が生じた場合の法的保護があまり期待できないため、ライセンサーにとって開示リスクが高い技術情報です。そのリスクに備えるために開示料としてイニシャルペイメントを設定することが行われます。
契約期間中の使用料を一括で支払う方式を指します。ランサムペイメントであればライセンサーとしては不払い(使用料回収不能)のリスクが避けられますが、ライセンシーにとっては事前にまとまった資金を用意することが必要になるため、できれば避けたい選択肢です。
ライセンスされた技術をもとにして生み出された製品の出来高(製造数量や売上高)に比例して課金される使用料です。ランニングロイヤリティ方式はライセンサーにとっては不払いのリスクがありますが、ライセンシーにとっては一般的に受け入れやすい選択肢です。
ランニングロイヤリティ方式では出来高に比例して使用料が増えますが、出来高が非常に小さいとライセンスの採算が取れないなどの問題が生じる恐れがあります。
そこで、最低限のライセンス収入を確保するために一定の出来高に達するまでの分は使用料を定額とする場合があります。この最低定額使用料をミニマムロイヤリティと呼びます。
ライセンシーに独占的使用権を与える場合、ミニマムロイヤリティを設定することである程度リスクをコントロールすることができます。
ミニマムロイヤリティを設定する代わりに、出来高が一定レベルを下回った場合には契約解除や契約変更を請求できるように設定する場合もあります。
提供される技術がライセンサーの主張するような働きを示すかどうかは、実際に使用してみるまではライセンシーにはわかりません。
技術に問題があることが判明した場合、それまでにかかったさまざまなコストが無駄になり、契約無効や損害賠償を求めて訴えることになれば訴訟コストも必要になります。
そのため、ライセンシーとしては技術の効果(生産能力など)についてライセンサーにある程度の保証を求めるのが賢明です。ライセンサーとしても、保証の範囲を明確にしておくことで無用なトラブルを避けることができます。
特許権や商標権は第三者からの訴えにより無効とされる場合があります。例えば、第三者がすでに公表していた発明と同じ内容を持つ特許や、第三者の著明な登録商標と酷似した商標は、たとえ正式な手続きを経て当局に登録済みであっても裁判により無効とされます。
したがって、特許や商標のライセンス契約の場合、特許権・商標権が無効とされる理由が存在しないことをライセンサーに保証してもらうのが一般的です。
提供された技術をライセンシーが改良し、新たな機能を付け加えてより便利なものとしたり、運用コストの削減に成功したりする場合があります。こうした改良技術の権利関係について、契約書で明らかにしておく必要があります。
ライセンサーとしては、改良技術の扱いをライセンシーの自由な判断に任せるのではなく、何らかの義務を規定して制限を加えたいと考えるのが自然です。
しかし、それによってライセンシーの研究開発意欲を損なったり、事業上の選択を過度にコントロールしたりすることになれば、不当な拘束条件のついた取引(独占禁止法第2条第9項第6号ニ[1]、不公正な取引方法第12項[2])と見なされる可能性が生じます。
以下のようなケースは原則として独占禁止法違反となります。
また、以下のようなケースも場合によっては独占禁止法違反となる可能性があります。
技術情報の秘密保持や流用防止はライセンサーにとって非常に重要な項目です。ライセンシーに対して適切な情報管理を求めるだけでなく、場合によっては第三者との共同研究開発を制限することも必要になることがあります。
また、業務提携解消時には可能な範囲で技術情報を返還・破棄し以後は一切利用しないという義務をライセンシーに課すことも必要です。
秘密保持を確実にするため、情報にアクセスできる者を限定した上でアクセス履歴の保存を義務づけることもあります。
共同開発提携は互いに技術を提供しあうもので、技術提携の一種と言えます。したがって技術提携契約の条項・検討項目は共同開発提携にも当てはまります。以下では共同開発提携に特有の条項・検討項目を解説します。
共同開発提携は現時点では明確な形のないもの(新技術・新製品)の開発を目指して行われるため、どのようなものをどのような目的で開発するのかについて契約書で具体的に限定しておくことが重要です。
共同開発提携では研究開発の進展に伴い必要な技術の範囲が変化する可能性があるため、提供すべき技術の範囲を契約締結時点で確定することは困難ですが、開発対象・目的を限定しておけば、技術の範囲をある程度絞り込むことができ、不本意な情報提供を求められるような事態が避けられます。
また、業務や費用の分担、開発成果の扱いなど、共同開発提携に関わるさまざまな問題について協議する際に、契約書に明記された開発対象・目的が解釈指針として役立ちます。
開発に伴う業務の分担は、開発の進展に伴い随時決定していかなければならない部分もありますが、少なくとも分担の基本方針については、開発目的などに照らして契約段階で決めておく必要があります。
業務分担と絡めて、費用負担についても(少なくとも基本方針を)規定しておくことが必要です。各自が行った業務は各自が費用を負担するとするケースもあれば、開発成果を多く利用する側が多くの費用を負担するようにするケースもあります(例えば産学連携で民間企業側の費用負担を重くするなど)。
共同開発で生み出される新しい技術・製品の権利の帰属(単独所有か共有か、共有の場合は持分比率をどうするか)は重要な問題です。開発費用をどのように分担し、開発された製品の販売利益をどう分配するかという問題とも密接に絡んでいます。
例えば、開発力が武器のベンチャー企業と大きな生産力・販売力を有する大企業が共同開発提携を行うケースでは、以下のような取り決めをすることが考えられます。
こうした問題は契約時に細部まで決定しておくのが難しい場合もありますが、基本的な点は明確にしておくことが必要です。
提携相手が共同開発事業に近い内容の研究開発を同時に進めていると、共同開発の成果と提携相手の単独開発の成果を区別するのが難しくなり、権利の帰属をめぐって紛争が生じる恐れが高くなります。
そうした事態を避けるため、共有される技術情報を共同開発提携の目的以外に使用することを禁じるだけでなく、提携期間中に近接したテーマの研究開発(独自開発や第三者との共同開発)を行うことを禁じる規定を設けることがあります。
生産提携では製品の仕様や生産方法などの技術情報が発注側から受注側に提供されるのが一般的です。そのため、技術提携の条項・検討項目は生産提携についても当てはまります。以下では生産提携に特有の条項・検討項目を取り上げます。
生産を委託する製品の品目・数量・価格、納期・納入方法などは状況に応じて変化していくため、提携契約書ではなく個別の発注書などで指定するのが一般的です。
提携契約書では、受発注の方法や価格の算定基準・協議方法、最低発注数量、分割納入・納期前納入についての定め、納期遅延が生じたときの処理方法、代金の支払い方法など、取引の流れと基本条件を設定しておきます。
発注側の資本金額が受注側よりも大きいと、下請法の「親事業者」と「下請事業者」の関係(同法第2条第7項・第8項[3])に該当する可能性があります。
その場合、親事業者である委託者は支払期日、代金設定、製品の受領・返品などに関する下請法の規定を遵守しなければならず、提携契約はそれに沿った内容にする必要があります。
生産提携では、原材料の種類・品質や製品の仕様・図面・製造工程などを発注者が指定するのが一般的です。発注者が自社の取引先などを調達先として提示したり、技術情報の秘密保持のため生産を行う工場を限定することを提案したりするケースもあります。
提携の進展に伴って原材料や生産方法の細目は変化していくことになるでしょうが、提携契約の段階で基本的な条件については合意しておくことが必要です。
生産提携で生産された製品は発注者の名前で販売されるのが一般的です。製品に発注者の商標・ブランド名を表示する場合には、表示する場所、大きさ、色などを契約書に明記しておく必要があります。商標・ブランド名の流用(提携外の製品への使用)を禁止する規定も必要です。
生産提携では、生産した製品の品質基準を契約書に明記し、それに基づいて受注側が品質保証を行うのが通例です。
品質基準は、発注者が指定した仕様に適合していることで十分とするケースもあれば、使用目的に適った品質・機能を有していることまで求めるケースもあります。
品質基準に加え、納入時の検品方法、保証期間、保証内容に反した場合の対応(代品請求・代金減額・損害賠償・契約解除など)について当事者間で合意しておく必要があります。
通例、生産提携により製造された製品は発注者の名義で販売されます。そのため、製品のユーザーが欠陥に気づいて苦情を訴えたり、製品の使用によって損害をこうむり製造物責任法に基づく訴訟を起こしたりした場合には、基本的には発注者側が矢面に立つことになります。
そうした事態に対し適切に対応するには受注者側との協力が欠かせないため、契約書に協力義務を規定しておくのが一般的です。
製造物責任で訴えられるのは通常は発注者です。発注者から受注者への指示がすべての原因であった場合には発注者が賠償責任を負えばよいのですが、受注者側にも問題があったという場合には、責任を分担しなければ不公平です。
したがって、賠償責任の分担に関する規定を盛り込んでおく必要があります。
製造物責任に関する対応は業務提携解消後にも必要になることがあるため、協力義務や責任分担は解消後についても規定しておくのが賢明です。
[1] 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(公正取引委員会)
[2] 不公正な取引方法(公正取引委員会)
[3] 下請代金支払遅延等防止法(公正取引委員会)
業務提携を効果的に実行していくためには提携企業間の協力体制の構築が欠かせません。また、将来的に担当者が異動する可能性を念頭に置いて情報管理を行うことも求められます。
業務提携を解消する段階では、在庫や雇用の扱い、費用・損失の負担などをめぐって利害対立が生じることがあるため、注意が必要です。とくに当事者の一方が自己都合で解消を要求する場合には交渉が難航し訴訟に発展するケースも少なくありません。
提携事業を円滑に遂行していくためには、業務スケジュールを的確に共有し、合同ミーティングなどで随時情報交換を行い、場合によっては人事交流なども進めていくことが必要になります。交渉段階でそうした点を協議し、協力体制や交流に関する規定を契約書に盛り込んでおくことが有効です。
また、提携事業を担当するキーパーソンの異動に伴って業務提携が希薄化することを避けるため、契約書は第三者から見ても(暗黙の了解なしに)明快に理解できる内容にし、関係資料は契約交渉時から組織的に管理するなどの工夫が必要です。
契約書があいまいだったり情報管理が担当者個人に任されていたりすると、担当者が変わる際に適切な引継ぎが行われず、それをきっかけにして関係が希薄化したり、将来的な計画について提携企業間で見解の相違が生じたりしてしまうことがあります。
業務提携は継続することを前提にした契約であるため、どうしても継続できない理由が生じたり相手方が重大な義務違反を犯したりした場合を除けば、一方的に解消することは難しいのが通例です。たとえ契約書に契約期間の定めを置いていたとしても、契約更新を一方的に拒否する行為は裁判で否認される恐れがあります。
解消を要求する側(解消者)と要求される側(被解消者)の間に以下のような事情がある場合、一方的な解消(契約解除・更新拒否)は裁判で否認される恐れが高くなります。
契約解消を行いやすくするためには、契約書に以下のような工夫を加えておくのが有効です。
在庫の処分
販売提携ではすでに仕入れた提携商品の在庫、生産提携では生産済みの提携製品や仕入済みの原材料の在庫が問題となります。
販売・生産を委託した側にとっては、提携終了により自らの関与が及ばないところで自社製品が流通してしまうリスクがあります。
受託側としては、在庫が無駄になることや、管理や処分のための費用が必要になることが懸念され、売約済みの取引がある場合には取引先との間でトラブルが生じる恐れもあります。
そこで、以下のような対応が求められることになります。
こうした対応は提携解消時に決めるのではなく、提携契約書に規定しておくことが望まれます。
提携事業のために設備を拡充したり、従業員を増員したりしていたため、提携終了後に整理が必要になる場合があります。
設備については、処分方法や処分費用の負担について当事者間で合意することで対応できます(なるべくならば契約書にそうした点を規定しておくべきです)
一方、人員整理はそう簡単ではありません。会社の都合で一方的に解雇することは解雇権の濫用と見なされ、裁判により無効とされます。
正規雇用の場合、まずは役員報酬減額、従業員の配転・出向、希望退職者募集、労働組合との協議などの対策を試みる必要があります。その上で、それでも人員整理が必要だと言えるならば、整理解雇が認められることがあります。
非正規雇用(期間の定めがある雇用)の場合、契約期間中の解雇は正規雇用の場合よりもさらに困難です。また、雇用継続を明言していたり、それを期待させる言動をしたりしていた場合には、期間終了時の更新拒否(雇止め)も無効とされます。
したがって、整理解雇を行う場合には提携終了前からかなり時間をかけて準備する必要があります。一方の会社が提携相手の雇用事情を顧みないで強引に解消を要求した場合、提携契約解除無効の理由として裁判で取り上げられることになるでしょう。
2020年に発表された業務提携のなかから、興味深い事例を5つ紹介します。
関東・中部・関西・北陸に1,300店舗以上の調剤薬局併設ドラッグストア「スギ薬局」を展開するスギホールディングスが、台湾の大手ドラッグストアチェーン企業大樹医薬と業務提携を結び、台湾国内でスギ薬局のプライベートブランド商品の販売に乗り出した事例です。
スギホールディングスは自社プライベートブランドの販売権と商標使用権を大樹医薬に提供するとともに、商品の陳列・販売方法、店舗オペレーションなどのノウハウの共有と人材交流を進めていくとしています[4]。
販売提携を中心にして、ノウハウの提供という技術提携の側面も合わせ持った事例と言えます。
ファミリーマートは無人決済型コンビニエンスストアの実用化を目指し、無人決済・無人オーダーなどの省人化技術を開発するTOUCH TO GO社と技術提携契約を締結しました[5]。
TOUCH TO GO社の無人決済店舗システムは、利用者の動きをカメラやセンサーでリアルタイムに認識し、利用者が手に取った商品を決済端末に自動的に記録します。利用者は商品を持って決済端末の前に行き、表示された商品リストを確認して支払いを行うだけで購入を完了できます。
無人決済型ファミリーマートの1号店は2021年春頃に開店が予定されています。
気象コンサルティングの専門事業を展開する日本気象協会とアパレル産業に豊富な知見・ネットワークを有する伊藤忠商事が共同開発提携を結び、アパレル向け需要予測システムの開発に乗り出しました[6]。
日本気象協会は気象データ解析に基づく需要予測コンサルティング事業を手がけており、電力・ガスなどのエネルギー需要の予測サービスに加え、POSデータと気象データを組み合わせて商品需要を予測するサービスも提供しています。
今回の業務提携は、アパレル産業の生産・販売計画と在庫管理を客観的な需要予測に基づくものへと変革することを目標としています。2021年中にユナイテッドアローズ、ナノ・ユニバースなどアパレル企業数社から売上データの提供を受けてテスト運用と効果検証が行われ、2022年春夏シーズンから本格的な運用が開始される予定です。
楽天と日本郵便は以前から物流事業での協業を行ってきましたが、Eコマースの進展とコロナ禍による「新しい生活様式」の広まりを受け、物流に関する戦略的な業務提携の締結に向けた基本合意書を取り交わしました[7]。
日本郵便の物流ネットワーク・物流データと楽天の受注・需要データ運用ノウハウを掛けあわせ、効率的な配送システムと柔軟な受け取りサービスを備えた物流DXプラットフォームを構築し、将来的にはプラットフォームを共同で運営する新会社の設立も検討していく予定です。
製薬業国内最大手の武田薬品は世界をリードする他企業と連携しながら新型コロナウイルス感染症治療薬の開発を推し進めており、ワクチンについては、米国のバイオテクノロジー企業2社との業務提携を通して日本国内向けに大規模な製造・販売を行うことを計画しています。
武田薬品は2020年8月に米Novavax社と業務提携を結び、同社から新型コロナワクチン製造技術の使用権を取得しました。国内での供給へ向け商品開発を行うとともに、年間2億5,000万回分以上のワクチン生産が可能な設備の構築を目指しています[8]。
11月には米Moderna社とも提携し、同社から5,000万回分のワクチンの供給を受けて製造販売を行うことを発表しています[9]。
[4] スギホールディングス株式会社と Great Tree Pharmacy Co., Ltd.との業務提携のお知らせ(スギホールディングス株式会社)
[5] ファミリーマートとTOUCH TO GOが業務提携 無人決済システムを活用した店舗の実用化に向け協業(株式会社ファミリーマート)
[6] 日本気象協会と伊藤忠商事、アパレル向け需要予測サービス事業で業務提携(日本気象協会)
[7] 日本郵便と楽天、物流領域における戦略的提携に向けて合意(楽天株式会社)
[8] Novavax社と武田薬品による日本における新型コロナウイルス感染症ワクチンに関する提携について(武田薬品)
[9] Moderna社および厚生労働省との提携による、新型コロナウイルス感染症ワクチンの日本における供給について(武田薬品)
業務提携は他社の経営資源を活用して事業成長を図るための取り組みのひとつです。M&Aや資本提携と違い資本の移動が伴わないため、互いに独立した関係を保ちながら多種多様な形態の協力関係を築くことが可能です。
その反面、関係が希薄化しやすいというデメリットがあり、提携開始後や提携解消時にトラブルや紛争が発生することも少なくないため、提携契約ではそうしたマイナス面をカバーする工夫を盛り込むことが求められます。
(執筆者:相良義勝 京都大学文学部卒。在学中より法務・医療・科学分野の翻訳者・コーディネーターとして活動したのち、専業ライターに。企業法務・金融および医療を中心に、マーケティング、環境、先端技術などの幅広いテーマで記事を執筆。近年はM&A・事業承継分野に集中的に取り組み、理論・法制度・実務の各面にわたる解説記事・書籍原稿を提供している。)
.png&w=3840&q=75)
■このようなお悩みはありませんか?
①M&Aの手紙は毎日届くがどこに依頼すればいいかわからない
②M&A会社との面談ではなく候補先がいそうか、売却金額はどのくらいかだけを知りたい
③自分と自社の人生が変わるM&Aの相手は、幅広い選択肢から自分で選びたい
M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ
■M&Aサクシードが選ばれる理由
①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約
②業界では珍しく契約なし、書類提出なしで売却相場がわかる「かんたん売却先検索」が使える
③多数の大手・優良企業が登録し、他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数
④M&A登録支援機関に認定されている
M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。
知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。
譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。