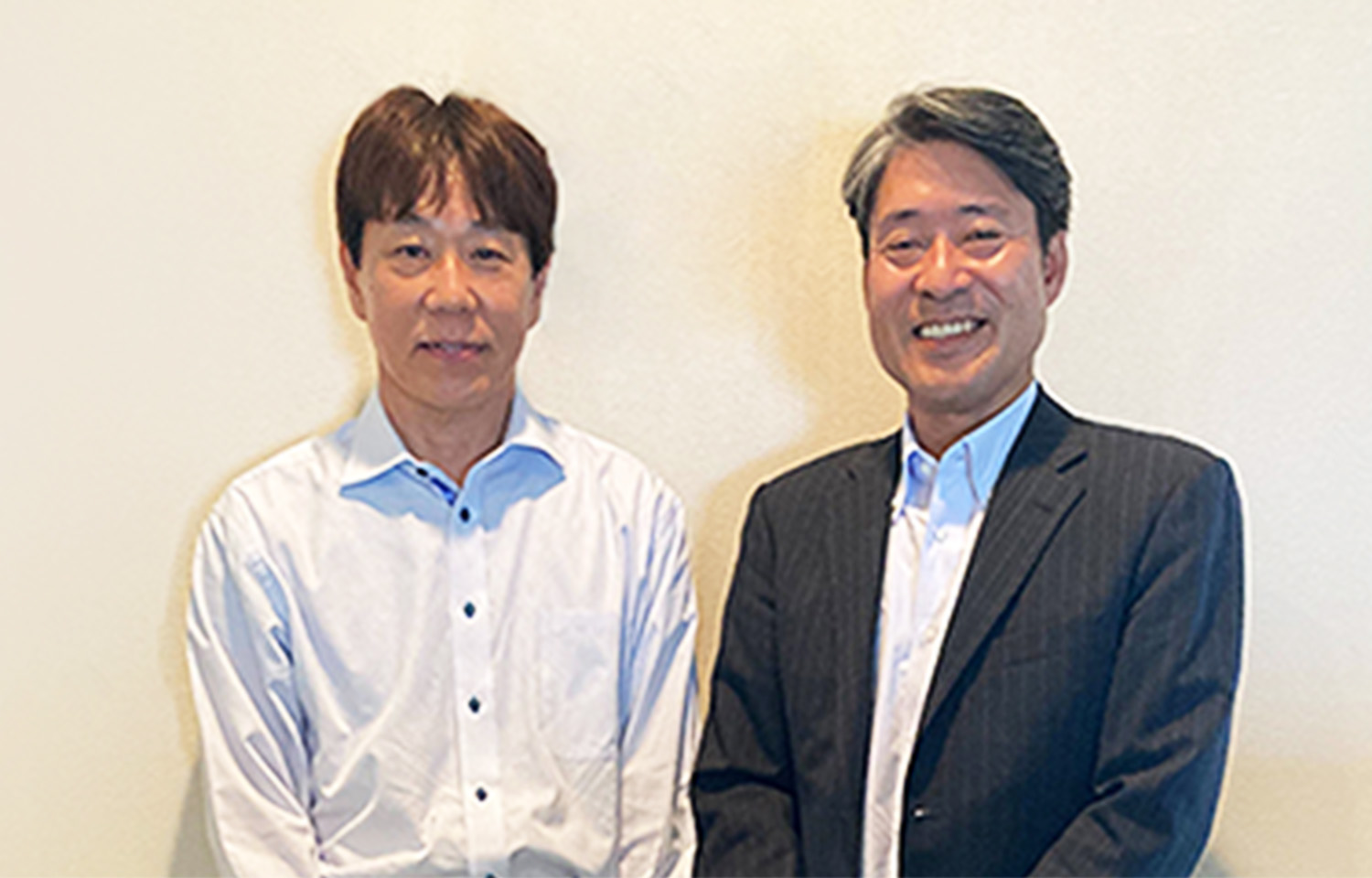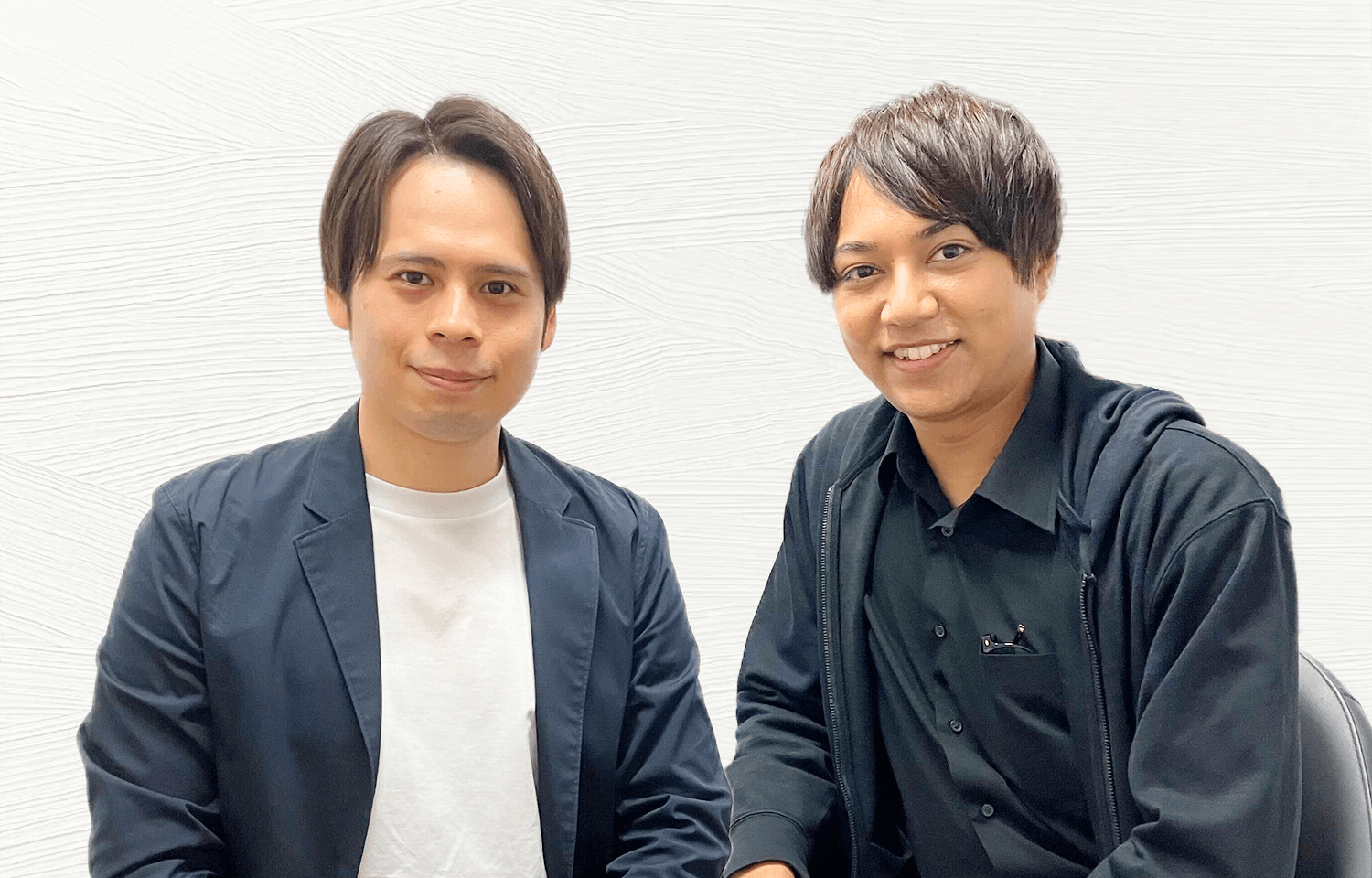- 家具
- 小売り
- 酒類
- 福岡県
「家具のまち」福岡県大川市で、製材業として1920年に創業した株式会社エトウ。100年の歴史の中で、常に新しいことに挑戦し続けてきた同社は、インテリア家具の設計開発、OEM家具の輸出入、家具のインターネット販売など、時代の流れに合わせて、事業構造の変革・拡大をしてきました。そんな同社が今回M&Aサクシードを通じてM&Aしたのは、同じ福岡県で100年以上続いている酒の小売販売を行う企業です。まったく異なる業界の企業を買収した経緯や、M&A後の取り組みや改革について、エトウ会長の江藤 義行 氏と社長の山﨑 彩 氏に伺いました。(2021年2月公開)
事業拡大と海外展開。新しいことに挑戦し続ける文化が強み
――100年の歴史を持つ家具製造・販売業を営むエトウの、特徴や強みを教えてください
山﨑社長 創業以来、製材業を続けてきたエトウは、1987年に経営不振に陥った地元の家具メーカーを譲り受ける形で家具製造業に進出しました。しかし、バブルの崩壊によって地元の家具に関連する企業の倒産が相次ぎ、製材機の数は100から10に、家具製造の企業は6分の1にまで激減。もちろん当社も大変な危機的状況に陥りました。

でも、苦しい時だからこそ新しい挑戦をするべきだと考えて、1990年にログハウス展示場を開設し住宅事業に進出〔(注)2000年に住宅事業部を売却し、当事業から撤退)〕。その後、中国、香港、ベトナム、マレーシアに海外法人や海外事務所を開設し、家具の輸入・輸出販売のグローバルサプライチェーンを構築しました。また、不振に陥ったネット販売業者を引き受ける形で、家具のインターネット販売業にも進出し、現在は10年ほど前に子会社化し、エトウグループの牽引役となって貢献しています。
エトウの強みは、家具製造で培った豊富な知識・技術、インテリア家具の設計開発力、そして東南アジアを中心とした海外ネットワーク等々100年続く企業でありながら、フットワーク軽く常に新しいことに挑戦し続けていることだと考えています。
――新しいことに挑戦し続けてきたエトウの文化が、今回のM&Aにもつながったのですね。
江藤会長 これまでも企業や事業単位のM&Aは実施しており、成長戦略に欠かせないものだと捉えています。企業を譲り受ければ、ビジネスも人材も獲得できますし、社内に新たな緊張感も生じます。それが会社にとって良い刺激となり、次の事業拡大のタネになると考えています。
新しい経営を受け入れてくれる従業員とともに、進める大改革
――今回M&Aをした企業の、どこに魅力を感じたのかを教えてください。
江藤会長 今回譲り受けた企業は酒の小売販売を行う企業で、エトウとは業種もビジネスも全く異なるように見えます。でも当社は以前から不況に陥った地元の小さな酒蔵への支援や佐賀大学農学部との麹の共同研究、またアメリカで麹を使用した製品を提供するカフェの出店などの取り組みをしていたので、酒・麹という分野は馴染みのある領域だったのです。

しかも、店舗は同じ福岡県内のかなり良い立地にあり、創業101年続く老舗酒屋というのもポイントでした。ディスカウント時代でどこの酒屋・酒造メーカーも厳しい中、101年も続いているのは本当に素晴らしいことだと思いましたね。
加えて、コロナ禍で飲食店が厳しい状況になり、業務用を扱っている酒屋は軒並み業績が落ち込んでいるのですが、今回譲り受けた企業は業務用を扱っておらず、業績が落ちていなかったのです。こうした様々な面から興味を持ち、成約に至りました。
――9月から酒屋を迎え入れ、どのようなシナジーを生んでいるのでしょうか。
山﨑社長 実は、店舗は少しだけ訪問できたものの、コロナ禍の交渉で直接社内を訪問できていなかったので、M&A後に知る事実がとても多かったのです。事務作業や能力は旧態依然としたもので、業務プロセスや職場環境も良い状況ではありませんでした。でも、逆に考えれば、改善すればプラスにしかならないと思いました。
しかも、すごく良かったのは、従業員の皆さんがとても前向きに新しい経営を受け入れてくれていることです。それが、潰れていく酒屋や酒造メーカーが多い中、100年以上続いた理由だと思いましたね。
実際、「ずっと改善や新しいことへの挑戦をしたかったけれど実行できなかった。でも、今は次々と改善を提案してくれるから嬉しい」と言ってくれる社員や、私達の経営の考え方を知って、パートから社員になりたいと言う人も出てきました。
業務プロセスやビジネスの改善は簡単なことではありませんが、従業員にとても恵まれているので、新しい酒屋へ向けての大改革も乗り切れると感じています。
M&Aは小さい企業を救い、生まれ変わらせるチャンス
――具体的に、どのような改革を進めていくのでしょうか。
山崎社長 まずは、店舗を改修します。もともと人が集まる場所に位置しているので、エトウの酒屋として、賑わいを作るのが当面の目標です。加えて、インターネット販売もテコ入れをして、前年比120%の売り上げを目指しています。
10年以上前に、業績不振で赤字だった事業を譲り受けたことがあるのですが、そのときも事業を再生させて業績を回復させたので、今回も同じように再生させたいと考えています。
何より今回は、自分たちも変わりたいという強い思いを持った従業員が揃っているから、今は想像ができていない変革も実現するものと確信しています。そして、いずれは海外に日本のお酒の文化を広めるような活動もできるといいですね。
――エトウ様のように、なかなかM&Aに一歩踏み出せない企業は多いと思います。そうした企業に向けて、アドバイスをお願いします。
山﨑社長 M&Aはニュースで聞くような大手企業と大手企業の大型案件だけではありません。M&Aサクシードをはじめ、インターネットで流通している小規模な事業単位の譲渡案件であれば、野心のある社員にM&A担当として動いてもらうこともできますし、企業としても社員としても成長機会につながります。
それに、小さい企業を救うチャンスにもなるんです。誰にも気づかれず、止む無く閉じていたような事業や企業も、インターネットで情報を発信すれば生まれ変わるチャンスになるし、譲り受け企業からしても、新しいチャレンジをするチャンスになる。事業を拡大する上では、間違いなく良い方法だと思っています。
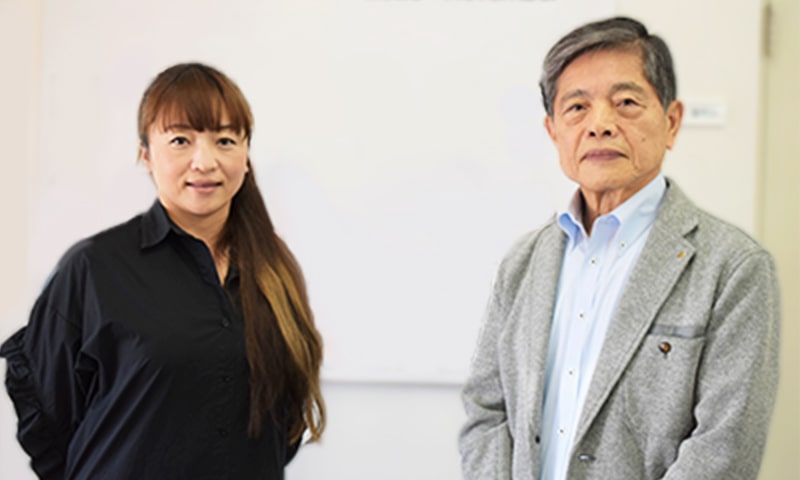
当社は創業100 年を迎えるにあたり「伝統とは革新し続けること。世界を見据えた挑戦の船出へ」というメッセージを掲げました。100年たったからと言って安心する、とどまるのではなく、またこれからがスタートだとたえず思って挑戦することが大切です。そのような思いをもって前進しています。
だからぜひ、我々と同じように地元で100年続くような老舗企業も、現状に満足するのではなく、常に「今からがスタート」という気持ちを持ってM&Aに挑戦してほしい。そうすれば、日本の未来は変わっていくと思っています。
コロナ禍でオンライン会議が当たり前になり、移動せずに新しい情報を収集できるようになったことも地方企業にとっては追い風です。だからエトウは、今後も積極的にM&Aを検討・実施したいと考えています。