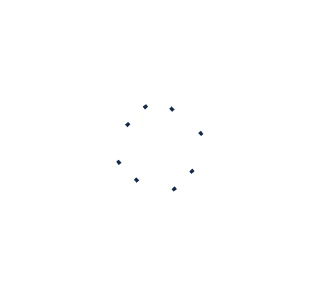
この記事では2020年9月までのM&A成約件数や譲渡金額の推移を紹介します。2019年に譲渡金額の大きかったM&Aランキングや、自社の事業売却を検討する会社の経営者が、コロナ禍で下した決断も紹介します。
中小企業庁が毎年発行している(同庁ホームページでも公開されています)中小企業白書2018年度版は、M&A仲介を手がける東証一部上場の3社(株式会社日本M&Aセンター、株式会社ストライク、M&Aキャピタルパートナーズ株式会社)の成約組数をまとめています。[2]
同白書によると、2017年は、中小企業のM&A成約件数が2012年比で3倍を超えています。中小企業のM&Aに関しては、仲介会社が関与しない例も多いと見られますが、増加傾向にあることは分かります。
2019年は、日本企業どうし(IN-IN)のM&Aと、日本企業による海外企業(IN-OUT)のM&Aの両方が過去最高となりました。リーマン・ショックを境に、日本企業が海外企業の買収に乗り出したことは、統計から読み取ることができます。
中小企業では、オーナー経営者の高齢化にともない、自分の会社を第三者などに譲る事業承継のニーズが経済してきたことも、M&Aの押し上げ要因になったと考えることができます。
ここで、国内でM&Aが増加している背景について考えてみたいと思います。一つ目は、国内市場の成熟化にあります。日本は高度成長期のように、人口が増える中で作ればモノが売れるような時代は過ぎ去り、逆に人口が減少に転じていることから国内市場は「パイの奪い合い」の様相を呈しています。
パイの奪い合いとして一番分かりすいのが、スーパーマーケットやコンビニエンスストアで、小売業界では過当競争から中小のチェーンが、M&Aによって大手に買収されていきました。コンビニ業界を例にとると、am/pmはファミリーマートに、スリーエフはローソンにそれぞれ吸収されています。
国内でM&Aが増加している二つ目の理由は、オーナー経営者の高齢化です。中小企業庁によると、引退の目安とされる75歳を超える中小企業経営者は、2025年までに約245万人と見積もっています。このうち約半数の約127万人が後継者未定と推計されます。
ここからは、新型コロナウイルス感染症が流行した2020年のM&A件数について、見ていきます。
トムソン・ロイターは、2020年4月1日、第1・四半期の世界のM&A(合併・買収)は28%減少し、2016年以来の低水準となった[3]と報じました。ロイターは新型コロナウイルスの感染拡大による経済への打撃が、3月に顕著になったことが背景にあったと見ています。
ロイターが引用したリフィニティブのデータによると、第1・四半期のM&Aは6980億ドルで前年同期の9640億ドルから28%減少。米国は半減して2520億ドル、アジアも17%減少し1429億ドル。欧州は倍以上に増えて2320億ドルになったといいます。
新型コロナの影響が深刻化する数週間前に、大型案件が成立したことが背景にあるとみられています。
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、主力事業の収益確保を優先しM&Aは停滞傾向です。一方、7~9月には買収額が1兆円を超える大型案件の発表が相次ぎ、金額ベースでは12兆円と12%増加したといいます。
リーマン・ショックの影響などで日本企業が関わる年間のM&Aの件数は11年まで減少しましたが、12年以降は連続して増加。今回対象の1~9月でも増加が続いたが、今年は9年ぶりに減少したことが分かりました。
特に海外企業が買い手または売り手となるM&Aが大きく減った。日本企業同士は5%減の2115件でしたが、海外企業が関わる件数は30%減の571件となり、新型コロナ禍で先行きの見通しが不透明な中、多くの国内企業は海外企業との再編を手控えていると分析しています。
国内については、Visionalグループのビジョナル・インキュベーション株式会社は、M&Aアドバイザー2名によるコロナ禍におけるM&A動向レポートを公表しています。[5] 同レポートから、お二方による分析を順番にご紹介します。
日本政府が緊急事態宣言を発出した2020年4月から5月は、企業が急激な売り上げの減少といった業績の悪化への対応に追われたせいなのか、会社や事業の売却を検討を取りやめる企業が多く見られたといいます。
また、コロナの収束が見通せず、将来に対する不安から譲り受け企業(買収を検討する企業)や投資家が待ちの姿勢に転じたため、M&A成約件数は減少したと見られています。
コロナの感染拡大が一旦収まり始めた6月頃から、コロナ禍の影響をあまり受けていない譲り受け企業がM&Aの検討を徐々に再開。なかには、競合が少なく、譲渡価格が低下傾向であるこの状況をチャンスと捉え、積極的にM&Aの検討を行う譲り受け企業も出てきたようです。
一方で、飲食業界やホテル業界をはじめ、コロナ禍の影響を大きく受けている譲り受け企業は、6月以降もM&Aの検討を停止しているケースが多く見られます。
2020年3~4月はコロナ禍の影響を受け、M&Aの検討を停止する企業が多く見られましたが、5月から企業・事業の買収検討を再開する企業が増えています。特に、コロナ禍において業績が好調なEC、動画、インターネット広告関連企業などが、積極的にM&Aの検討を再開しています。
一方で、緊急事態宣言の発出後に、Webメディアを運営する企業から、売却希望の問い合わせが急増。Webメディアは最終的には売却することを前提に運営されていることが多く、WebメディアのM&A市場はコロナ禍以前から成熟していました。コロナ禍の影響で先行きが不透明になり、売却に不安を抱いた企業が増えたため、問い合わせが急増したものと思われます。
[3] 企業買収が世界で減少、新型コロナで2016年以来の低水準(トムソン・ロイター)
[4] 日本企業のM&A件数、9年ぶり減、1~9月(日経電子版)
[5]「M&Aサクシード」利用M&A専門家によるコロナ禍のM&A動向レポート発表 中小企業のM&Aは活性化、2021年はM&A件数増加予想
次に、コロナが広がる2020年以前の国内におけるM&Aの推移について見ていきます。
1999年以降、日本でのM&Aが急増しました。蟻川靖浩経済産業研究所によると、1990年代には500件程度で推移していたM&A件数は、2000年以降大幅に増加し、2004年には 2,211件と10 年前に比べて約4倍に増加しました。[6]
同研究所は、1990 年代後半から2000 年代前半においては、IN-IN(国内企業同士のM&A)の取引件数が急速に増加したと分析しています。1980 年代後半において平均232 件であったIN-INの件数は、2000年代前半には平均1497件となっており、約6.4倍に増加したといいます。
また、全M&A件数に占めるIN-IN の割合は、1980年代後半には平均44.6%でしたが、2000年代前半においては平均76.3%とその比率を高めていました。近年のIN-INの取引の特徴としては、業界内の国際競争の激化等を背景にした業界内再編という点があげられる(同研究所)としています。
実際に、松下電器産業(現パナソニック)は、2004年3月、松下電工への出資比率を32.8%から52.7%へ引き上げ、連結子会社化しました。
内閣府経済社会総合研究所によると、国内M&Aは、1999年・2000年および2004年・2005年に急増し、その後2005年から2007年まで2,700件台の高水準を維持したといいます。
ところが、同研究所によると、リーマンショックにより、M&Aは2008年が約1割減、2009年が18%減と、ピークから約3割落ち込みました。[7] 2010年は各国の金融・経済対策が一応奏功し、世界のM&Aは回復の兆しを見せたが、日本企業が絡むM&A件数は1,707件と前年比12.8%のマイナスとなり、2003年ごろの水準に戻ったといいます。
中小企業においても、新事業展開や商圏拡大等を目的として子会社・関連会社を設立する企業も多いと見られます。買収・新設別に子会社を増加させた企業数の推移について見たものである。
2006年度に比べると、子会社・関連会社の新設を行った企業数は減少しているのに対して、買収により子会社・関連会社を増加させた企業は約1.8倍と増加傾向にあることが見て取れる。中小企業において、新設による企業グループ化よりも、他社の買収を選択することが増えているといえる[8]そうです。
[6] M&Aの経済分析:M&A はなぜ増加したのか(蟻川靖浩経済産業研究所 )
[7] 内外M&A事情調査研究報告2011(内閣府経済社会総合研究所)
[8] 中小企業白書2017年度(中小企業庁)
ここで、2019年に公表された国内のM&A買収金額上位10社について、ご紹介します。
アサヒグループホールディングスは、ビール世界最大手のアンハイザー・ブッシュ(ベルギー、ABI)から、豪州の全事業を160億豪ドル(約1兆2096億円)で買収することで合意しました。
買収対象はABIの子会社であるカールトン&ユナイテッドブリュワリーズ(CUB)を中心とするビール・サイダーに関連する全事業となります。ABIの子会社であるCUBが譲渡対象となりました。CUBはトップブランド「カールトン」を中心に、幅広い品揃えをもちます。
アサヒビールなどを中核とする飲料メーカーのアサヒグループホールディングスは、2016年以降、海外で相次ぎM&Aを加速してきました。アサヒグループホールディングスは、「Great Northern」をはじめとする有力ブランドの取得により、日本、欧州、豪州の3極を核としたグローバルな事業基盤を築くとしています。[9]
昭和電工は2019年12月、日立制作所子会社の日立化成を、TOB(株式公開買い付け)により、子会社化すると発表しました。昭和電工が設立した完全子会社であるHCホールディングスを通じて、日立製作所が保有する全ての日立化成株式を取得しました。
昭和電工は、今回のM&Aについて、日立化成の持つコア技術を組み合わせることによって、次世代通信規格である5G、半導体、自動車の電動化などに着目した7事業領域での成長を目指すとしています。[10]
ソフトバンクグループは2019年12月、傘下のZホールディングス(HD、旧ヤフー)とLINEが経営統合に向けた最終契約書を締結したと発表しました。同年11月に、両社の親会社であるソフトバンクと、韓国のネイバーを交えた4社での最終合意に至ったためです。
経営統合後はソフトバンクとネイバーが折半出資した新会社の傘下にZHDを置き、ヤフーやLINEを子会社化しました。折半出資会社はソフトバンクの連結子会社となりました。[11]
Zホールディングス(HD)は2019年に、約4007億円をかけて、TOB(株式公開買付け)によりZOZOの発行済み株式を取得すると発表しました。
Zホールディングスは、ヤフーを傘下に持つ持ち株会社です。2019年10月1日に持株会社体制に移行し、商号を「ヤフー株式会社」から「Zホールディングス株式会社」に変更しました。
ZOZOはファッションECサイト「ZOZOTOWN」を運営する会社で、国内ファッションECサイトでは圧倒的なシェアを誇っています。ヤフーは、「PayPayモール」というネット上の電子ショッピングモールを運営しており、ZOZOTOWNをPayPayモール出店させることで、集客力を高める狙いがあったとされます。 [12]
東京センチュリーは、2019年12月、米国航空機リース会社アビエーション・キャピタル・グループの完全子会社化しました。親会社である米国大手生命保険会社パシフィック・ライフが保有するアビエーション・キャピタル・グループの持分取得を完了し、完全子会社化したものです。
東京センチュリーによるアビエーション・キャピタル・グループの買収価格は、2,9億米ドル(約3,24億円※、アドバイザリー費用などの手数料を含む)となります。[13]
※ 1米ドル当り108.90円(2019年12月5日現在)で換算
アステラス製薬は、2019年12月、米国のバイオテクノロジー企業のオーデンテス・セラピューティクス(本社:カリフォルニア州)の買収手続きに入りました。
アステラス製薬は、同社の間接子会社を通じて、オーデンテス・セラピューティクスの全発行済み株式を株式公開買い付け(TOB)により取得。オーデンテス・セラピューティクスは、アステラス製薬の子会社となりました。[14]
日本ペイントホールディングス(HD)は2019年4月、豪州の塗料メーカーであるデュラックスグループの買収が完了したと発表しました。
デュラックスグループは、オーストラリアやニュージーランドを中心として、塗料・DIY用品の製造販売事業を手がける企業です。同グループは、豪州証券取引所に上場していましたが、日本ペイントの子会社となったため、豪州証券取引所において上場廃止とな
りました。[15]
いすゞ自動車は2019年12月、スウェーデンの商用車大手ボルボ・グループとの戦略的提携の手始めとして、ボルボ・グループが保有するUDトラックスとUDブランドで展開している海外事業を、いすゞに譲渡することを合意しました。
UDトラックスは、いすゞグループの傘下に入ることによって、ボルボ・グループとの協業による相乗効果を狙います。さらに2022年以降、いすゞとUDトラックスは一部車型の共有を行うとしています。 [16]
大日本住友製薬は2019年10月、欧州創薬ベンチャーの英ロイバント・サイエンシズと、戦略的提携に関する正式契約を結びました。この提携には、大日本住友製薬によるロイバント・サイエンシズ子会社5社の株式取得や、他の子会社6社の株式取得に関するオプション(一定の条件下での交渉権)も得ました。
さらに、大日本住友製薬はロイバント・サイエンシズの株式を10%以上の取得し、ロイバント・サイエンシズのヘルスケアテクノロジープラットフォーム(基盤)を取得する内容も含まれています。 [17]
完全子会社の富士フイルムは2020年12月、日立製作所の画像診断関連事業を買収すると発表しました。発表当初の買収見込み金額は、は約1790億円としていました。
富士フイルムは、日立製作所の画像診断関連事業を買収することによって、富士フイルムのメディカル事業のさらなる拡大を目指す方針としています。日立製作所の画像診断システムは、CT(コンピューター断層撮影装置)、MRI(磁気共鳴断層撮影装置)、X線診断装置など、幅広い製品群を持っていました。[18]
[9] アサヒグループホールディングスのプレスリリース(アサヒグループホールディングス株式会社)
[10] 日立化成株式会社を連結子会社化(昭和電工株式会社)
[11] プレスリリース(ソフトバンクグループ)
[12] プレスリリース(ソフトバンク株式会社)
[13] 米国航空機リース会社Aviation Capital Group の持分取得完了について
[14] 米国Audentes社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ(アステラス製薬株式会社)
[15] 豪州塗料メーカー DuluxGroup Limited 社の買収完了について(日本ペイントホールディングス株式会社)
[16] いすゞとボルボ・グループ、商用車分野での戦略的提携に関する覚書を締結(いすゞ自動車)
[17] Roivant Sciencesとの戦略的提携に関する正式契約の締結(大日本住友製薬)
[18] 日立製作所の画像診断関連事業買収に関するお知らせ(富士フイルムホールディングス株式会社)
次に、世界のM&Aの推移について見ていきたいと思います。まずは米国(アメリカ合衆国)からです。
デロイトトーマツによると、米国のM&Aマーケットは2019年上期に、前年同期比で件数はやや減少傾向にありましたが、金額ベースでは上昇しています。[19] トランプ政権下のアメリカの経済は堅調で、金融緩和による金利水準の低さもあり、M&Aが活発化していたと見られます。
CFIUS(Committee on Foreign Investment in the United States: 対米外国投資委員会)による審査の強化や、米中貿易戦争の影響もあり、活発であった中国企業による買収が2017年以降大きく減少し、2019年上期においては欧州企業による米国企業へのインバウンド投資が目立っている状況でした。[19]
EYストラテジー・アンド・コンサルティングが今年12月に公表したリポートによると、新型コロナウイルス感染症の流行下において、欧米などのM&A市場が総じて前年比二ケタ減となった一方で、アジア・パシフィック地域は同8%減と、回復力の強さを示しました。[1]
同リポートは、アジア・パシフィック地域のM&Aは、国内の業界再編やテクノロジー案件に引っぱられる形で、2020年第3四半期に、同四半期としては過去最高の業績を上げたとしています。欧米に比べて、アジア・太平洋地域の方が、コロナによるダメージからいち早く回復したことが伺えます。
世界のM&A案件数は、2020年上半期に4分の1近く(23%)減少し、アジア・パシフィック地域のみでも第1四半期に20%下落しており、これはGFC時代の減少状況を二年先行する速さです。
しかし、この大流行からのM&Aがどのくらい回復していうのかについては、アジア・パシフィック地域と世界のその他地域との間に乖離が生じています。
年初来の9ヵ月間で見ると、アジア・パシフィック地域の案件数減少が前年比8%であるのに対し、米州(南北中米)では前年比20%減、EMEIA(欧州、中東、インド、アフリカ)では前年比15%減と、はるかに厳しいものとなっています。
[19] 新型コロナウイルスがM&Aに及ぼす影響の厳しさは世界金融危機を上回るも、アジア・パシフィックの多くの国はいち早く回復しつつある(EYストラテジー・アンド・コンサルティング)
これまで見てきたように、リーマン・ショックやコロナ禍など、世界的な経済危機が起きると、一時的にM&Aの件数が落ちてくることが分かりました。ただ、2020年の夏頃からアジアなどでM&Aは回復基調にあることから、コロナの感染が収まってくれば、2021年にかけて、M&Aが回復してくる可能性もあるでしょう。
M&A・事業承継のご相談ならM&Aサクシード
.png&w=3840&q=75)
M&Aのご相談ならビジョナルグループが運営する日本最大級のM&AマッチングサイトM&Aサクシードがおすすめ
■M&Aサクシードが選ばれる理由
①希望する条件の会社がすぐに見つかる機能が多数最短37日でスピード成約
②納得できる売却先が見つからない方向けにあなたの希望条件で買い手を探すことが可能
③他社にはない異業種からの驚きのオファーで地域や業種を超えた大きなシナジー事例が多数
M&Aサクシードは、成約するまで無料の「完全成功報酬制」のM&Aマッチングサイトです。
知識・経験が豊富な専任担当者が相談から成約に至るまで伴走します。
譲渡・譲受いずれもご相談も無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。