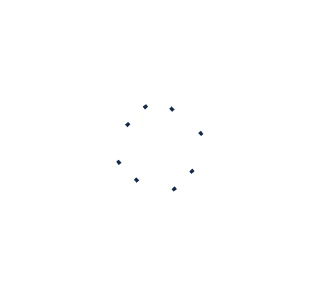
今回は大企業・中小企業別、業界別に厳選したM&A事例40選を紹介します。国内・海外の大企業事例から中小企業事例まで、譲渡・譲り受け企業の概要、M&Aの目的・M&A手法、成約に至るまでを解説します。コロナ禍以降の最新M&A事例も紹介します。(執筆者:産業経済紙 経済部記者 宮里秀司)
日本で公表されているM&A成約件数は2004年に2,000件を超えた後、2017年に3,000件を超え、更に2019年には4,088件と急増しています。2020年には3,730件とやや減少したものの、依然として高い水準となっています。[1]
2020年の日本企業によるM&Aは、新型コロナウイルス感染症の影響により、4-5月は停滞したものの、6月以降徐々にこれまでと同じ水準にまで回復しています。[2]コロナ禍の企業経営は更なる合理化や資金調達、新たな市場に合わせた事業の変化が必要な局面にあります。買収企業はDXをはじめとした新規事業への迅速な投資や、規模の拡大とシナジー効果を求めてM&Aに投資し、売却企業は差し迫った資金調達の必要性によってM&Aを模索しています。
事業承継M&Aプラットフォーム「M&Aサクシード」では利用企業を対象に「M&Aに関するアンケート」を行いました。その結果、9割以上の企業が今後M&A市場が「活性化する」と回答しています。2020年1~5月の譲渡希望企業の新規登録者数は前年同期比4.3倍となり、M&A市場活性化の傾向が見られます。業界再編や企業のDXが進む中で、2021年以降はますますM&Aを活用した企業統合が加速すると考えられます。
この章では、2021年に行われた最新のM&A事例を3例紹介します。
なお本記事では、資本業務提携も広義の意味でのM&Aと捉えております。
売り手は、Eコマースをはじめとして合計で70を超えるサービスを運営している楽天です。
買い手は、郵便事業を全国的に展開している日本郵政です。
楽天と日本郵政がM&Aを実施した目的は、DXや物流などの領域における連携強化です。
具体的には、以下の業務提携が想定されています。
両社のM&Aでは、「日本郵政が持つ物流網・荷量データ」と「楽天が持つ物流領域における受注データの運用ノウハウ」の相互活用によるシナジー効果が期待されています。[3]
両社のM&Aでは、第三者割当増資のスキームが活用されました。
具体的には、日本郵政が楽天の増資を引き受けました。
出資額はおよそ1,499億円、出資比率は8.32%です。
出資金の払込みは、2021年3月29日でした。[4]
売り手は、メッセージの送受信を行えるサービス「LINE」を運営するLINEです。
買い手は、ECサイトや広告サービスなどをはじめとした200を超えるサービスを展開するZホールディングスです。
両社が経営統合を図った目的は、「各企業の既存事業強化」と「新規事業への投資」の2点です。
本件のM&Aにより、「マーケティング事業」、「フィンテック事業」、「新規事業・システム開発」、「集客」という4つの部分でシナジー効果が期待できるとのことです。[5]
両社は以下の流れで経営統合を図りました。
上記のとおり、複数の企業・スキームが絡む複雑なM&Aであった点が特徴です。
なお経営統合は2021年3月に完了しました。[8]
ココカラファインは、日本全国で1,444店舗のドラッグストア・調剤薬局を展開する会社です。
マツモトキヨシは、日本全国で1,755店舗のドラッグストア・調剤薬局を展開する会社です。
業種を超えた競合企業の新規参入や異業種との競争、商圏の狭小化などにより、ドラッグストア市場では厳しい経営環境が続いていると言われています。
このような中で両社は、さらなる事業の成長を実現する目的でM&Aを行います。
本件の経営統合で両社は、商品の共同開発や販促戦略のデジタル化などを実現することで、連結ベースで営業利益約200億円のシナジー効果を得られると発表しています。
両社の経営統合では、株式交換や新設分割、吸収分割など、複数のM&Aスキームが用いられる予定です。
この経営統合を通じて、ココカラファインはマツモトキヨシHDの子会社となります。
最終的な効力発生日は、2021年10月1日(予定)です。[10]
[3] 日本郵政グループと楽天グループ、資本・業務提携に合意(楽天)
[4] 第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分の一部払込完了のお知らせ(楽天)
[5] 経営統合に関する最終合意の締結について(Zホールディングス)
[6] ソフトバンク・韓ネイバー、LINE株のTOB終了(日本経済新聞)
[7] LINE 株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果に関するお知らせ(Zホールディングス)
[8] ZホールディングスとLINEの経営統合が完了(Zホールディングス)
[9] 株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインとの経営統合に関する経営統合契約の締結のお知らせ(マツモトキヨシホールディングス)
[10] 株式会社マツモトキヨシホールディングスと株式会社ココカラファインとの経営統合に関する経営統合契約の締結のお知らせ(マツモトキヨシホールディングス)
それでは、2020年に入って行われた日本企業による最新のM&A事例を見ていきます。
スピードウェイは、米国オハイオ州に本社を構える小売業です。コンビニエンスストア事業と燃料小売り事業の運営をしています。
セブン&アイ・ホールディングスは、日本のコンビニ業界では最大手です。セブン&アイは弁当やおにぎり、パンや「中食」と呼ばれる惣菜やおかずを、オリジナルブランドとして自社で開発するなど、独自の商品力に特徴をもっています。
セブン&アイ・ホールディングスは、日本のコンビニ市場が飽和状態にあるなかで、成長を海外に求め、北米市場でコンビニ事業の拡大を目指しています。セブン&アイ傘下のセブン-イレブンは、全米で約9,800店舗を運営しており、業界最大手となっています。
セブン&アイ子会社の米国法人が、スピードウェイの発行済み株式を取得しています。取得価額は約2兆2176億円です。
Enecoは、オランダ、ベルギー、ドイツの3ヵ国を中心に、再生可能エネルギーを中核とした発電、電力・ガストレーディング、電力・ガス小売り、地域熱供給の各事業を展開しています。
顧客ベースの規模はオランダで2位のポジションにあります。約120万kWの再エネ資産を保有しています。2007年に他社に先駆けて再エネ開発を開始、11年からは消費者向けに100%グリーン電力を供給しています。
三菱商事は日本トップクラスの規模と収益力を誇る総合商社です。近年はグループの商材やサービスを組み合わせることで、エネルギーマネジメント関連のサービスを充実させています。
中部電力は、商圏とする中部地区以外にも関西や関東などに進出し、海外展開にも乗り出しています。
三菱商事とEnecoは、2012年から3件の欧州洋上風力発電事業(123万kW)で欧州最大規模の蓄電事業(5万kW)で協業してきました。三菱商事と中部電力によるエネコ買収は、欧州での再エネネルギー事業拡大を狙ったものです。
今後、ロッテルダム市等の既存株主及びEneco内での手続きを経て、株式売買契約を締結した後、三菱商事と中部電力が共同で設立した新会社(Diamond Chubu Europe B.V.)を通じて、最大100%の株式を41億ユーロ(約5千億円)で買収しました。[11]
生活支援機器の製造・販売、航空機機装品及び軽合金構造物の製造・販売、ハニカム及びその加工品の製造・販売、汎用コンテナ、輸送支援機材全般を手がけています。
ベインキャピタルはプライベートエクイティ(PE)、ベンチャーキャピタル、ヘッジファンド、債券運用などを手がける米国の投資会社です。1984年の設立以来、ベインキャピタルは750億ドルの資産を運用してきています。1984年米国本社設立で、2006年に日本事務所を開設しました。
ベインキャピタルによる昭和飛行機工業の買収は、昭和飛行機工業の非公開化を目的としています。筆頭株主が昭和飛行機工業に対し、経営管理ノウハウの提供や新たな成長に向けた支援を行うことで、企業価値の向上を目指すとしています。
ベインキャピタル系のケイマン籍の会社が、昭和飛行機工業に株式公開買い付け(TOB)を実施しました。昭和飛行機はTOBに賛同意見を表明し、49.80%を保有する親会社の三井E&SホールディングスはTOBに応募し、昭和飛行機株を売却しました。[12]
Santherは、ブラジルで機能性フィルム、粘着シート及び粘着剤等合成樹脂材料の製造・加工および販売を手がけています。
大王製紙は、1943年の設立の総合製紙メーカーです。1979年以降はティッシュの「エリエール」をはじめ、乳幼児用紙おむつ「GOO.N」などのブランドを育ててきました。
大王製紙は海外展開で、M&Aを成長手段の一つととらえており、衛生用の紙製品に対する需要増加が期待されるブラジル市場への進出を決めました。大王製紙はブラジルへの進出を足がかりとして、南米全域への事業展開も視野に入れているといいます。
大王が51%、丸紅グループが49%をそれぞれ出資するブラジルの現地法人(合弁会社)が、Santher全株式を取得します。[13]
島忠は中堅のホームセンターです。家具・インテリア雑貨(カーテン・カーペット・インテリア小物など)や、ホームセンター商品を扱う小売店を展開しています。60店舗(2020年8月末現在)を展開しています。
家具・インテリア用品の製造・販売国内外に計607店舗を有し、製造から物流、販売まで全て自社でてがけています。
島忠をめぐっては、同業大手で「ホーマック」などを展開するDCMホールディングスがTOBを実施中でした。その後、DCMとニトリとの間で争奪戦となり、島忠はいったん同意していたDCMによるTOBへの同意を取り下げ、ニトリのTOBに応じることとしました。TOBの実施は2021年1月を予定しています。
ニトリは2021年1月に、1株5500円で島忠株のTOBを開始する予定です。ニトリは島忠のTOB成立後に、完全子会社化を目指します。[14]
NECディスプレイソリューションズは、日本電気(NEC)の子会社です。液晶ディスプレイ、ビジネスプロジェクターなどの製品や関連サービスを世界で展開しています。
電気通信機器や電気機器、電子部品の製造・販売を主体とする電機メーカーです。現在は台湾資本の傘下に入り、連結売上高は2兆2,712億円(2020年3月期)、連結従業員数は51,402名(2020年9月末現在)です。
国内市場に強いシャープと、欧米事業を中心としたNECディスプレイソリューションズが同じグループとなることで、グローバル展開で相互補完関係が見込めることから、M&Aに踏み切りました。
シャープはNECディスプレイソリューションズの株式を66%取得し、子会社とします。NECは引き続き、NECディスプレイソリューションズの株主としてとどまります。シャープとNECは、NECディスプレイソリューションズを合弁会社として共同運営することで合意しました。[15]
Origamiは2012年に会社を設立し、2016年にスマホ決済サービス「Origami Pay」の提供を開始、同サービスは、全国の様々な業種、業態の店舗やサービスに導入。また、2018年9月には全国256の信用金庫の中央金融機関である信金中央金庫と資本・業務提携しています。
メルペイは、メルカリの100%子会社として、2019年2月にスマホ決済サービス「メルペイ」の提供を始めました。2019年4月に「メルカリ」での利用実績などを基に、商品購入代金を翌月にまとめて支払える「メルペイスマート払い」にも対応しています。
M&Aの狙いはメルペイとメルカリ、Origami、信金中金の4社共同で、地域の中小事業者への「メルペイ」導入の推進していくことです。
2020年1月、メルカリの子会社でスマホ決済サービス提供のメルペイが、Origamiの株式を取得して子会社化することを発表した。
[11] オランダ総合エネルギー事業会社Eneco社の売却入札における優先交渉権獲得(三菱商事)
[12] ベインキャピタル系が昭和飛行機にTOB、1株2129円(REUTERS)
[13] ブラジルにおける衛生用品メーカーの株式取得(子会社化)に関するお知らせ
[14] 株式会社島忠の株券等に対する公開買付けの開始及び同社との間の経営統合契約の締結に関するお知らせ(株式会社ニトリホールディングス)
[15] 株式取得によるNECディスプレイソリューションズ株式会社の子会社化(合弁会社化)に関するお知らせ(シャープ株式会社)
譲渡企業のマイトリップ・ネットは、国内最大のインターネット宿泊予約サイト「旅の窓口」を運営していました。
楽天はEコマース(電子商取引)、トラベル、デジタルコンテンツなどのインターネットサービス、クレジットカードや銀行・証券・電子マネー・スマホアプリ決済などのフィンテック(金融)サービス、携帯キャリア事業といったモバイルサービス、プロスポーツなどさまざまな分野で70を超えるサービスを展開しています。
楽天は株式上場によって、社会的な信用力や資金調達力を得ました。楽天は上場直後から、M&Aを活用した規模拡大を積極化しています。楽天は国内旅行において、JTBグループに次ぐ2位の取引高に成長させました。自社サイト「楽天トラベル」の強化が狙いでした。
2003年9月に、楽天は国内最大のインターネット宿泊予約サイト「旅の窓口」を運営するマイトリップ・ネットを323億円で、株式買収により子会社化しました。[16]
ドクタープログラムは、通信販売による化粧品会社でした。ドクタープログラムは機能性基礎化粧品「トリニティーライン」を中心としたスキンケア領域を主力としていました。
大正製薬は一般用医薬品(OTC)で国内トップクラスの製薬会社で、品揃えや販売網の拡大が経営課題でした。
大正製薬は、セルフメディケーション領域の事業強化のため、通信販売事業を拡充する必要がありました。ドクタープログラムの商品開発ノウハウや販路を活用することで、事業規模の拡大を図ることができました。
武田薬品工業は、ドクタープログラムの親会社であったキョーリン製薬ホールディングスから、ドクラープログラムの株式を買い取りました。[17]
ヴァイオス・メディカルは米国の医療機器メーカーベンチャーです。ヴァイオス・メディカルは心拍数、呼吸数、心電図等を計測できるチェストセンサの開発や、計測機器に関わるソフトウェアやクラウドサービスなども展開しています。
心拍数、呼吸数、心電図等を計測できるチェストセンサの開発と、それらをモニタリングするためのソフトウェア、クラウドサービス等を開発・提供しているヘルスケア IT 分野のベンチャー企業です。
村田製作所は、セラミックスを基とした電子部品の開発・生産・販売を手がける総合電子部品メーカーです。材料開発やプロセス開発、商品設計、生産技術及び関連するソフトウェア開発も行っています。
村田製作所は、市況の変化が激しい電子部品を主力製品としています。収益が安定しているヴァイオス・メディカルの買収により、村田製作所はグループ全体の収益を下支えする効果を見込んでいました。
村田製作所は2017年に、現地の子会社を通じた三角合併という手法により、ヴァイオス・メディカルの株式を取得し、完全子会社としました。買収費用は114億円です。[18]
2つ目に紹介するM&A成功事例は、味の素が近年に行った買収です。味の素は、トルコにある2社の食品会社を買収しており、合計3つの会社を統合しています。
譲渡企業は2社あります。一つはキュクレ食品という会社で、トルコで液体調味料やピクルスなどの製造・販売を行っています。もう一社がオルゲン食品社で、粉末調味料・粉末スープ・デザートなど加工食品の製造・販売を手がけています。
譲り受け企業は、味の素です。「味の素」に代表される調味料や、インスタント食品・飲料・健康食品などを製造・販売する、日本の大手食品メーカーです。味の素は海外にも展開しており、事業所は約35カ国・地域におよびます。
味の素は海外展開において、東南アジアなどで存在感を示しています。トルコはアジアやと欧州の間に位置し、中東とも隣接するため、商品開発や販路の拡大にも役立っています。
味の素の100%子会社である、トルコのイスタンブール味の素食品販売とキュクレ食品、オルゲン食品を統合しました。[19]
サンジェルマンは「サンジェルマン」ブランドのパン屋を展開する、ベーカリー事業が主力の会社です。2002年5月に、日本たばこ産業(JT)がサンジェルマンの全株式を取得し、JTの100%子会社となりました。
テーブルマークは、冷凍食品やその他食料品の製造・販売お手がける国内大手冷凍食品メーカーです。これまでに冷凍ハンバーグや冷凍エビフライ、冷凍さぬきうどんなどの画期的商品や、ヒット商品を多く生み出してきたことでも知られます。
JTは、グループ会社で中国製冷凍餃子の中毒事件が起きたことがきっかけとなり、グループの加工食品事業・調味料事業を旧加ト吉(現テーブルマーク)に移管しました。その延長線上として、加ト吉がサンジェルマンを傘下に収めました。
加ト吉(現テーブルマーク)が、テーブルマークのJTグループ全株式を取得し、2008年7月に加ト吉(現テーブルマーク)の100%子会社となりました。[20]
[16] 100%子会社 楽天トラベルとマイトリップ・ネットの合併について(楽天株式会社)
[17] キョーリン製薬ホールディングス株式会社の連結子会社である ドクタープログラム株式会社の株式取得に関するお知らせ
[18] Vios Medical, Inc.の買収完了について(株式会社村田製作所)
[19] 味の素(株)トルコおよび中東における海外コンシューマー食品事業を拡大(味の素株式会社)
[20] 日本たばこ産業株式会社の食品事業部門との事業統合について(カトキチ)
日本テレコムは、1984年に設立された固定通信事業者です。のちにインターネットサービスプロバイダー事業も手がけました。
ソフトバンクグループは、携帯電話事業などを手がける子会社を持つ持ち株会社です。子会社数は1,475社(2020年3月末現在)に上り、関連会社は455社(同)あります。
その目的は、日本テレコムのODNユーザーをスムーズにYahoo!BBに移行し、ネットワークへの投資を抑えることでコスト削減を図ることでした。
ソフトバンクは2004年、米国の投資会社リップルウッド・ホールディングス傘下にあった日本テレコムを買収しました。ソフトバンクが買収した日本テレコムの営業強化やコスト削減などを進め、買収からわずかから3年ほどで、経営を立て直し、グループの収益力にも寄与するようになりました。[21]
ZOZOはファッションECサイト「ZOZOTOWN」を運営する会社です。国内ファッションECサイトでは圧倒的なシェアを誇っています。
Zホールディングスは、ヤフーを傘下に持つ持ち株会社です。2019年10月1日に持株会社体制に移行し、商号を「ヤフー株式会社」から「Zホールディングス株式会社」に変更しました。
Zホールディングス傘下のヤフーは、「PayPayモール」というネット上の電子ショッピングモールを運営しています。ZOZOTOWNをPayPayモール出店させることで、集客力を高める狙いがありました。Zホールディングスグループのモバイル決済サービス「PayPay」を、ZOZOTOWNに導入する計画もあると新聞報道等で伝えられています。
Zホールディングス(HD)は約4007億円をかけて、TOB(株式公開買付け)によりZOZOの発行済み株式を取得。今年11月14日にZOZOの買収が完了したことを発表しました。ZホールディングスによるZOZO株式の保有比率は、50.1%(議決権ベース)となりました。[22]
譲渡企業は、米国のたばこメーカーのRJRIです。日本たばこ産業(JT)が買収をしようとした当時、世界最大のたばこメーカーでした。
JTは主力のたばこ事業のほか、医薬事業、食品事業を手がけ、連結 従業員数は61,975人(2019年12月31日現在)となっています。
JTはRJRIの買収当時、海外におけるたばこの販本数を1,000億本にする目標を掲げていました。消費者の健康志向やたばこにかかる税金の引き上げなどもあり、JTの販売本数が伸び悩んでいました。JTは今後も成長を続けていくためには、大型の企業買収が必要と判断し、海外に活路を求めました。
JTはRJRIをクロスボーダー(国境を越えた)取引として、約9,400億円で買収し、従来比約10倍となるたばこ販売本数を得ることができました。[23]
富山化学は研究開発型の製薬企業で、抗ウイルス薬などで世界的な実績を残しています。
富士フイルムは従来の写真技術を生かした診断領域から、予防や治療からへ事業領域を拡大する目的で本案件を実施しました
富士フィルムは2000年以降、7000億円弱規模のM&Aを実施してきました。写真関連事業のリストラクチャリング(事業構造改革)にのりだし選択と集中を進る一方で、近年は医療分野でM&Aを積極化していました。
2008年3月に富山化学を株式公開買い付け(TOB)により連結子会社化しました。[24]
アンハイザー・ブッシュ・インベブ(ベルギー、ABI)は、ビール世界最大手です。ABIの子会社であるCUBが譲渡対象となりました。CUBはトップブランド「カールトン」を中心に、幅広い品揃えをもちます。
アサヒグループホールディングスは、アサヒビールなどを中核とする飲料メーカーです。アサヒグループホールディングスは2016年以降、海外で相次ぎM&Aを加速してきました。
アサヒグループホールディングスは、「Great Northern」をはじめとする有力ブランドの取得により、日本、欧州、豪州の3極を核としたグローバルな事業基盤を築くとしています。また、買収によるブランド力やマーケティング力の強化も見込んでいます。
アサヒグループホールディングスはビール世界最大手のから豪州の全事業を160億豪ドル(約1兆2096億円)で買収することで合意した。買収対象はABIの子会社であるカールトン&ユナイテッドブリュワリーズ(CUB)を中心とするビール・サイダーに関連する全事業となります。[25]
[21] 日本テレコムの買収について(ソフトバンク株式会社)
[22] 当社子会社(Zホールディングス株式会社)による株式会社ZOZO株式に対する公開買付けの結果及び子会社(孫会社)の異動に関するお知らせ(ソフトバンク株式会社)
[23] JTグループの歴史(JT)
[24] 富士フイルムグループ の成長戦略(富士フィルムホールディングス株式会社)
[25] アサヒグループホールディングスのプレスリリース(アサヒグループホールディングス株式会社)
これまで大企業のM&Aを取り上げてきましたが、ここからは、中小企業の事例もご紹介します。
COMBOは、VRおよびAR開発を強みとする会社です。
テクノモバイルは、Webシステムやモバイルアプリの開発を主力事業とする会社です。
売り手は、新型コロナウイルスにともなう経営の先行き不安を解消するために、会社売却を行いました。
一方で買い手は、地方への事業拡大と優秀なエンジニアの獲得を実現するために、売り手企業とのM&Aを行いました。
2020年、COMBOは株式譲渡のスキームを用いて、テクノモバイルへの会社売却を実行しました。
COMBOは、テクノモバイルに対して90%の株式を譲渡しました。
会社売却後、買い手と売り手はシステム開発の業務における連携体制を確立しました。[26]
売り手は、富山県で書籍や販促物などの企画・印刷のサービスを手がけるアヤトです。
買い手は、福岡県で一般商業印刷業を運営するスキャトです。
当時売り手の経営者は、自身の高齢化にともない事業承継を検討していました。
しかし、子供や社内の人材に後継者になってもらうように打診したところ、良い返事を得られなかったとのことです。
そこで、社員の雇用を継続する目的で、廃業ではなく第三者に対する事業承継(M&A)を行いました。
一方で買い手がM&Aを行った目的は、売上のさらなる増大です。
同業種が主な顧客であったスキャトと異なり、売り手企業は公共の仕事を多く手掛けていました。
買い手の経営者は、顧客層が異なることでシナジーを生み出せると期待してM&Aを行いました。
両社のM&Aは、株式譲渡によって実施されました。
売り手の経営者は、あらかじめ経営者が社員に対してM&Aを行うことを公表していました。
そのため、社員からの理解をスムーズに得ることができました。
一方で買い手の経営者は、M&Aを行って以降、週の半分をアヤトで過ごし、社内組織図の明確化や、ルールの明文化などを行い、経営の統合を進めています。
双方の経営者が積極的に行動したことで、M&Aおよびその後の統合がスムーズに進んでいる事例と言えるでしょう。[27]
売り手は、愛知県で施設の常駐警備事業を手掛けているライフ・コーポレーションです。
買い手は、紹介予定派遣や人材派遣など、総合的な人材サービス業を手掛けている日輪です。
売り手企業は、経営者の高齢化に伴い、事業承継を行う目的で会社売却を実施しました。
一方で買い手企業は、自社の求人サイトに登録している高齢人材の働き先を確保するために、警備事業を手がける売り手企業とのM&Aを行いました。
ライフ・コーポレーションは、株式譲渡の手法を用いて、日輪への会社売却を行いました。
売り手企業の経営者は、M&Aが完了した時点で引退する予定でした。
しかし、買い手企業の社長から要望を受けたことで、現在も社長業を継続しています。[28]
売り手は、システム開発およびインフラ構築のサービスを手がけるIT企業です。
買い手は、金融分野に特化したシステム開発・支援を主力事業とするSDアドバイザーズです。
売り手企業は、社外への事業承継を目的にSDアドバイザーズへの会社売却を行いました。
元々は社内で事業を引き継ぐ予定でしたが、前社長の奥様が体調を崩し、社内承継が困難になったことでM&Aを決断したとのことです。
一方で買い手企業は、非金融システムの分野に参入するために、売り手企業を買収しました。
コウイクスは、株式譲渡の手法で会社売却を実行しました。
SDアドバイザーズの傘下企業となったことで、売り手企業では「従業員の主体性向上」や「経理のデジタル化」といった効果を得ることに成功しました。[29]
売り手は、静岡県の伊豆で予約が取れない旅館として有名となっている「桐のかほり 咲楽」です。
買い手は、フォトスタジオを主力事業とし、結婚式場の運営で業績を拡大してきた「小野写真館」です。
売り手企業は、後継者不足を理由に、外部の第三者に事業承継を行う目的でM&Aを実施しました。
一方で買い手企業は、当時コロナ禍でブライダル事業の売上が約40%減少していました。
そこで、業態を転換するために異業種である売り手とのM&Aを行いました。
売り手は、事業譲渡の手法により、旅館を小野写真館に譲渡しました。
売り手側が買い手側の経営理念に共感したことで、3ヶ月という短さでM&Aが成約しました。
買い手企業では、M&Aで旅館を獲得したことで、旅館に併設されたウエディングフォトスタジオを始めたり、旅館全館を貸し切った挙式を開催したりすることに成功しています。
売り手と買い手双方の良さが融合した点で、異業種M&Aに特有のシナジーが創出された事例と言えます。[30]
売り手は、ネイルチップの販売サイト「ミチネイル」を運営するミチです。
買い手は、石川県に本社を置く織物メーカーである丸井織物です。
売り手企業は、自社事業の選択と集中を行う目的で事業売却を行いました。
一方で買い手企業は、デジタルマーケティングを強みとする「オリジナルラボ」という子会社を有していました。
また売り手企業も、ECサイトに関するノウハウを有しており、リスティングやSEO対策を強みとしていました。
そこで買い手の丸井織物は、シナジー効果を創出するために売り手とのM&Aを実施しました。
両社は、事業譲渡の手法でM&Aを実施しました。
M&Aが完了した後、丸井織物は売り手企業について無駄なコストを削減する施策を行いました。
その結果、2ヶ月という短い期間で利益率を15%から40%まで改善することに成功しました。
また売り手企業のオーナーは、新規事業を始めつつ、引き続き買い手企業のネイル事業に協力してくれているとのことです。
買い手側が売り手オーナーの考えに寄り添うスタンスをとったことで、良好な関係性を構築できているのです。[31]
売り手は、国内で7店舗の本場インド料理店を運営するスニタトレーディングです。
買い手は、チェーンのカレー店運営や、カレーの商品開発・販売を行うゴーゴーカレーグループです。
売り手企業は、当時手作りの商品をデパートなどに卸していましたが、十分な利益を得られていませんでした。
そこで、自社商品の味を広めるために、EC販売やPR活動を得意とする買い手企業に工場を売却しました。
一方で買い手は、インドカレーブランドを展開しており、その過程でハラール料理を作れる工場が欲しいと考えるようになりました。
そこで、ハラール料理を作ることができる工場を持つ売り手企業とのM&Aを実施しました。
スニタトレーディングは、事業譲渡のスキームを用いて、ゴーゴーカレーグループに自社工場を売却しました。
工場を売却したことで、ゴーゴーカレーの販路を使って自社ブランドを展開しやすくなりました。
一方で買い手は、ハラール料理のブランドや新メニューを開発できるようになりました。[32]
ENCOMは、広島県に拠点を置くITシステム開発会社です。
アイティエルホールディングスは、インフラ系のシステム開発会社を4社、複数の事業を展開する事業会社を6社持つ企業です。
売り手は、事業承継を目的にアイティエルホールディングスとのM&Aを実施しました。
一方で買い手は、さらなる事業拡大を目的に、ENCOMとのM&Aを行いました。
両社のM&Aは、株式譲渡の手法で実施されました。
コロナが原因で直接話すことが困難であったものの、売り手経営者の柔軟な対応により、3ヶ月というスピード成約につながりました。
買い手企業では、グループ横断でさまざまなサービス・製品を展開する「プラットフォーム構想」を進めています。
そのために、ENCOMには自社の経営資源を活用してもらうと同時に、自治権を持って強みを発揮してもらうとのことです。
売り手は、ECサイトなどのWeb開発、および受託でのアプリ開発を手がけるデジタルクエストです。
買い手は、関西と首都圏をメインに総合リユース業を手がけるトレジャー・ファクトリーです。
売り手企業は、「新しい事業領域で多種多様なサービスを作り出す」という目的で、この意思を尊重してくれた買い手企業に会社売却しました。
一方で買い手は、技術力の強化を目的に、システム開発を主力事業とする売り手とのM&Aを行いました。
このM&Aで買い手は、「新サービスの開発に必要なリソース・ノウハウが不足している」という課題を解決できました。
売り手は、株式譲渡の手法で会社売却を行いました。
自社サービス開発を手がける買い手企業のグループに参画したことで、社員からは「自分たちの意思でサービスを開発できるようになった」というポジティブな意見が挙がったとのことです。
一方で買い手企業でも、開発者から「自分たちが持っていない強みを持っている」という前向きな声が挙がっており、双方が満足できるM&Aであったと言えます。[34]
株式会社Choiseeは、ガジェット・IT系ツールのレビューメディアの運営をしていた、宮城県にある会社です。
大阪のWeb関連会社は、Webサイト制作、オウンドメディア制作・運営、システム開発などを手がけていました。譲り受け企業のWeb関連会社は運営メディアを増やすことで、事業の拡大を目指していました。
メディア運営をオーナー経営者が一人で手がけていたため、個人でメディアの更新などに対応することが難しくなり、事業譲渡を検討していました。オーナーは自分で買い手企業を探せるプラットフォームを探し、M&Aマッチングサイトに登録しました。
譲り受け企業となったWeb関連会社は、複数メディアを運営しているところが、オーナーの希望にかない、事業の譲渡金額もオーナーが納得いくものだったことから、事業譲渡が成立しました。
株式会社LIGは東京・上野のWeb制作会社で、サイト制作や自社メディアやコンテンツの制作、地方創生事業、シェアオフィス、英会話スクールなど多様な事業を展開しています。
埼玉県のIT企業です。
LIGは事業者や個人と、旅行者をマッチングするCtoC(個人間)プラットフォーム「TRIP」を運営していました。全国各地の遊びや観光商品を売買できるサービスでしたが、事業を伸ばす担当者が不在であったため、事業売却の道を選びました。
事業譲渡です。LIGは、M&Aマッチングサイトを介して、譲渡の候補先となった埼玉県のIT企業に事業を譲渡しました。売却にあたり、LIGのCTOが一定期間、サービスの運営を支援するコンサルティング契約を締結。LIGによる保守運用の提案も、譲り受け企業が受け入れました。
千葉県にあるハワイアンカフェ2店舗を運営する企業です。本業はアパレルで、事業ポートフォリオを見直し、選択と集中をするために店舗を引き継いでくれる企業を探していました。
オークニ商事は、コンサルティング会社として設立された企業です。現在は、飲食店や福祉介護施設などを、全国193拠点で展開しています。
オークニ商事は売り上げの拡大を目指しており、自前で新たに事業を立ち上げるのではなく、自社にはないブランドを持っている企業を買収候補先として、求めていました。
事業譲渡です。オークニ商事にとって、譲り受け企業を探す期間は2ヶ月程度しかありませんでした。すぐにM&Aマッチングサイトに掲載すると、翌日にはメッセージが届いたというのが今回の経緯です。
有限会社東航は、1984年創業の運送業で、輸出入貨物、産業廃棄物の処理、事務所の移転、引越を主力としていました。東航の経営は創業者である先代から、二代目社長に引き継がれ、無借金経営を続けてきました。
TRUTH LOGISTICS株式会社は、海上・航空輸送、通関ロジスティクスサービスを展開する企業で、M&Aによる事業拡大を目指していました。
東航の2代目社長は、70歳を目前に控えており、後継者がいませんでした。このため2代目社長は従業員の雇用や取引先との関係を維持するために、会社の譲渡を検討。東航はM&Aマッチングサイトに登録したところ、買収先を探していたTRUTH LOGISTICSとマッチングが成立しました。
株式譲渡です。TRUTH LOGISTICSが東航の株式を買い取る形で、M&Aが成立しました。
アポロ工業は埼玉県の金属プレス加工メーカーで、プレス金型に関する高い技術力をもつ高付加価値企業でした。
新栄工業は、千葉県で事業を営む金属プレス加工メーカーです。
新栄工業は事業のさらなる成長を目指し、M&Aを検討しており、M&Aマッチングサイトに登録しました。70代のアポロ工業の社長は、高齢を理由に引退を検討していましたが、後継者不在のため、第三者に会社を譲渡することを考えていました。
株式譲渡です。新栄工業によるアポロ工業のM&Aにより、アポロ工業は新栄工業の傘下に入りました。アポロ工業の看板や工場や従業員は引き継ぎ、取引先から信頼を寄せられていた「アポロ工業」という看板も残しました。
株式会社立山高圧工業は、ホースと継手の加工販売を手がけるオーナー企業でした。先代は70歳を超え、ホースや継手を収集していた職人気質の方でした。
日本ニューマチック工業株式会社は、年商が100億円を超えていました。譲渡企業の立山高圧工業と事業内容が近い会社でした。
立山高圧工業の創業社長は事業承継として、親族外によるM&Aを希望していました。買収に名乗りを挙げた譲り受け企業の日本ニューマチック工業は、ホースと継手の加工販売に対する理解がありました。
株式譲渡です。M&A仲介会社のインテグループが、譲渡企業である立山高圧工業と譲り受け企業の日本ニューマチック工業との間に入りました。インテグループは、株式譲渡後の経営戦略や譲渡価格などの条件について調整をして、M&Aが完了しました。
A社は、静岡県内で長い業歴を誇る建設関連業者です。代表者は高齢でしたが、取引先からの信頼も得ていて業績は堅調でした。
B社は建設関連事業を営んでいました。周辺領域への事業拡大を図る中期経営計画も策定していましたが、人材やノウハウが不足していました。
A社は当初、廃業を決意し静岡県事業引継ぎ支援センターに相談しました。ところが、同支援センターは、A社に対し他社への事業引継ぎを提案したところ、A社の代表者が同意しました。一方のB社は、M&Aによる事業拡大を目指していました。
事業譲渡です。静岡県事業引継ぎ支援センターは、取引金融機関と連携し、B社に対してA社のM&Aを提案。最終的に、B社がA社の建設業に関わる部門だけを対象に、事業を譲り受けることで決着しました。[35]
A社は年商4億円の事務機器製造業で、業績不振におちいっていました。
B社は年商13億円の事務機器製造業で、A社とは同業で、事業拡大を目指していました。
A社は赤字体質であったため、債務超過になってしまう恐れもあったため、大口取引先から同業のB社への会社売却を勧められました。
事業譲渡です。B社はA社の財務状況が良くないと判断したため、B社からの株式譲渡には関心がありませんでした。このため、A社はB社の土地と設備だけを買い取るという、営業権の譲渡が行われました。A社は、B社から受け取った営業譲渡の代金で、会社を精算し、負債を処理しました。[36]
新潟県にあった有限会社大基通信システムは、小さな内線電話工事会社でした。大基通信システムの人員は社長とその妻、従業員1名でした。
シルバー人材を活用するための企業組合です。
大基通信システムの社長が急逝したことにより、妻と従業員が二人で事業の継続することを決めましが、顧客離れが進んだため、売り上げは三分の一まで急減しました。事業の引き継ぎ手も見つかりませんでした。
事業譲渡です。M&Aとは異なり、企業組合を結成し、電信関連の地元中堅企業がスポンサーになる枠組みにより、事業を引き継ぎました。相談から半年で、企業組合を結成し事業の引き継ぎを終わらせました。[37]
A社は年商3億円の運送業で、トラックを約20台保有していました。精密機器の輸送にも対応できる会社でしたが、売り上げが落ち込み赤字決算で、資金繰りが厳しい状況にありました。
B社は、通信・電子機器製造業を営む年商15億円の企業です。
A社は実質債務超過という財務状況でした。一方で、B社は自社で製造する精密機器の運送を委託していた業者に不満を抱いていたため、製品の輸送を自前で行うことを検討しており、精密機器が輸送できる運送業者のM&Aを検討していました。
株式譲渡です。B社はA社の財務リスクを引き受ける形で、取引が成立しました。A社社員の従業員は、B社が全員引き継ぎました。異業種間のM&Aとして、B社からA社への100%株式譲渡として行われました。[38]
株式会社リブネット(従業員30名、資本金1億円)は、三重県伊勢市にある図書館業務の総合プロデュース企業です。図書館委託業務やソフトウェア開発販売、コンサルティングなどの事業を手がけていました。
東電通(現株式会社ミライト)は、電気通信工事業者の大手です。組織再編により(株)ミライトとなりました。
リブネットは、システム開発への投資がかさんだため、資本増強の必要がありました。そこで、リブネットの社長は、東電通の社長(当時)にリブネットへの出資を仰ぎました。
株式譲渡です。ミライトが、投資ファンドら外部投資家が保有するリブネットの株式を取得し、資本提携するに至りました。[39]
[26] 【M&A事例】VR/AR開発企業価値が評価されてスピード成約(M&Aサクシード)
[27] 親子3代続く富山県の印刷会社を、福井県の若手社長が経営する印刷会社に譲渡【M&A事例】(M&Aサクシード)
[28] インターネットだからこそ実現したスピードマッチング。最初のメッセージから1ヶ月でM&Aが実現【M&A事例】(M&Aサクシード)
[29] 金融システム開発会社が、非金融システム開発会社をM&Aし、事業拡大(M&Aサクシード)
[30] 【M&A事例】小野写真館様と旅館咲楽のシナジー効果とは?(M&Aサクシード)
[31] シナジーを生むM&Aによって、買い手企業と売り手企業の双方がwin-winの関係に【M&A事例】(M&Aサクシード)
[32] 1+1=100になるM&A。パートナーを組むことで鮮明になった世界展開【M&A事例】(M&Aサクシード)
[34] 「能動的」に売り手企業を探したい。攻めのM&Aが最適な企業との出会いを創出【M&A事例】(M&Aサクシード)
[35] 静岡県事業引継ぎ支援センター(静岡商工会議所)
[36] M&A事例集(東京商工リサーチ)
[37] 〈事例5〉(有)大基通信システム(事業承継・引継ぎポータルサイト)
[38] M&A事例集(東京商工リサーチ)
[39] 事業の承継(中小企業白書2017年版)
M&Aが失敗するパターンで真っ先に挙げられるのが、買収先企業の売り上げ見込みといった事業計画が、買収当初見込んでいた予想を大きく下回ったり、収益が赤字になったりすることです。競争環境の変化や市況悪化などの外部環境によって、想定が外れるケースです。
次に、海外企業や本業以外の事業分野の会社を買収する場合のリサーチ不足や、見込みの甘さです。特に中南米や中東といった政情が不安定な地域では、政変や地域紛争といった経済要因以外のリスク要因が致命的な結果を招きかねません
さらに、近年、脱炭素化が叫ばれるように、世界的な経営の潮流に乗り遅れた投資をすることもリスク要因となります。もし、海外で石炭火力発電を主力とする会社を買収した後に、石炭火力発電所の新規建設を認められなくなったら、買収効果がマイナスになる恐れもあるのです。
見落とされがちなM&Aの落とし穴としては、買収先の従業員がまともに働かなかったり、待遇の良いライバル企業に引き抜かれたりすることで、製品やサービスの質が保てなくなり、収益が悪化することです。人的リスクも事前によくリサーチする必要がありそうです。
それでは次に、M&Aの結果として損失が出てしまったり、当初の目論見どおりとならなかった事例を紹介します。
2006年に東芝は、アメリカの原発大手ウェスチングハウス(WH)を買収しました。ところが2011年に起きた東日本大震災を機に、原発事業に世界的な逆風が吹きました。
世界で原発の新増設に急ブレーキがかかり、WHの業績が急激に悪化。東芝は3,300億円というのれん代を計上していたため、2,600億円もの減損損失が発生しました。天災などにより外部環境が急激に変化することで、事業買収の目論見が外れるリスクがあることが分かる結果となりました。。
日本の総合商社である丸紅は、成長戦略の一環として、2012年にアメリカの穀物大手ガビロンを約2,880億円買収しました。当時の買収金額は、
丸紅は米国から中国市場への大量輸出を当て込んでいましたが、中国政府がガビロンによる寡占化を嫌い、中国への輸出が見込み通り増えませんでした。結果的に丸紅は、ガビロン買収にかかったのれん代約500億円を損失として計上することになってしまいました。
キリンホールディングスも海外企業のM&Aで苦戦しています。キリンホールディングスは2011年、ブラジルのビール大手のスキンカリオール約3,000億円で買収しました。キリンがスキンカリオールを買収した直後にブラジルの景気が悪化したため、2015年に減損損失1,100億円を計上ました。キリンは217年、オランダのハイネケンにスキンカリオールを約770億円で売却しました。
NTTコミュニケーションズは、念願の米国進出を果たしましたが、それがあだになってしましました。NTTコミュニケーションズは、約6,000億円を投じ、インターネットサービスプロバイダ(ISP)とホスティングサーバ提供事業を行うベリオを2000年に買収しました。
ベリオの業績はNTTコミュニケーションズによる買収後も低迷。そして、買収から翌年の2001年9月の中間期決算において、NTTコミュニケーションズはベリオについて5,000億円の減損損失を計上することを余儀なくされました。
第一三共は2008年、インド最大の後発医薬品(ジェネリック)会社であるランバクシー・ラボラトリーズを約4800億円で買収しました。しかし、インド国内の工場での品質管理問題が起きたことによって、業績が急速に悪化しました。
品質問題を受けて、米国政府がランバクシー・ラボラトリーズ製のジェネリック医薬品の輸入を停止したのです。第一三共は2015年,ランバクシー・ラボラトリーズをインドの同業大手に売却することになり、ランバクシー・ラボラトリーズに関する減損処理も発生しました。
コピー機で知られるリコーは、世の中のペーパーレス化が進み、買収した米国で相次ぎ減損損失を計上する事になりました。オフィスで紙を印刷する需要が、米国では急速に落ちていたからです。一つは2008年に買収した、米国の大手事務機ディーラーのアイコンオフィスソリューションズに関する1400億円の減損損失です。もう一つは2014年に買収した国のITサービス企業のマインドシフトに関する減損損失は400億円でした。
資生堂は2010年に米国のベアエッセンシャルを約1800億円で買収しました。ベアエッセンシャルは、テレビショッピングを中心として自然派化粧品を販売していましたが、予想通りに業績が推移しなかったため、資生堂は2013年3月期と2018年3月期で合わせて約950億円の減損処理を行いました。
LIXILグループは2014年にドイツの水栓金具大手のグローエを、約4000億円で買収しました。ただ、グローエの中国子会社で不正会計問題が発覚したことにより、2016年3月期までの3年間で660億円の損失がでてしまいました。
日本板硝子は2006年、世界3位のガラスメーカー、英ピルキントンを約6000億円で買収しました。わずか数年の間に、外国人社長が相次ぎ辞任し。10年間で6度の最終赤字を出してしましまいました。
富士フイルムホールディングスは2018年1月、米国のゼロックスの買収で合意しました。ところがゼロックス株主からの反発があり、合弁は解消されることになりました。結果的にゼロックスは保有していた富士ゼロックス株式の売却などによって、約2500億円を手にした一方で、富士フイルムホールディングスにとっては、合併の解消により得るものはほとんどありませんでした。
【執筆者プロフィール】
産業経済紙 経済部記者 宮里秀司
産業紙の記者として23年にわたり、日銀や東京証券取引所、金融業界、投資ファンド、M&A仲介会社などを取材。現在は、経済部で財務省、国税庁、金融庁を担当。業界再編や事業承継に関する豊富な取材経験をもつ。